こんにちは、桐生真也です。
よく人の言い間違えに皮肉を言ったり、虐めるように指摘することを”揚げ足取り”なんて言いますよね。
元々は”揚げ足を取る”ということわざがあって、それが慣用句になっていったようです。
テレビなどで見る会見の様子ではまさに揚げ足を取ろうとしている感じがして、記者ってどうしてこうも嫌味なんだろうとか思ってしまいます。
そういえばことわざって小学校の国語の時間に習って以来ですが、結構ためになる言葉も多いですよね。
気になる!
そもそもことわざってどれくらいの数があるのでしょうか?
調べていくのは大変そうですが、気になってしまいました。
根気よく言葉と意味を見ていきたいと思います。
浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。
気ままにお付き合いいただけたら幸いです。
色々なことわざを見てみよう
そもそもことわざって何種類ぐらいあるのだろうと調べてみたら、はっきりとした数はわからないものの、5万~6万ものことわざがあるようです。
ことわざは日本だけの文化ではなく、世界中でそういった言葉を見ることができます。
最古のものでは紀元前2000年頃のメソポタミア文明のシュメールに記録が残されていて、 「君は見つけた物については黙っているくせに、 失った物のことだけは話している」という言葉があるようです。
意味としては人間の身勝手さを表しているとされていますが、何千年経っても人間性というのは変わらないことがわかりますね。
日本で記録がある最古のものはあの有名な「古事記」の中にいくつか出てくるようですね。
同じような意味や言葉選びをしていることわざもあり、「壁に耳あり障子に目あり」ということわざも、イギリスでは「畑に目あり、森に耳あり」となっているようです。
人種や性別、立場が変わろうとも、こういった残されて受け継がれてきた言葉に同じ人間であると感じられるのは面白いと感じました。
ここからは私がこれは共感できると感じたことわざをご紹介していきますね。
衣食足りて礼節を知る

生活にゆとりができれば自然に礼儀正しくなってくるということ。
お金があれば生活にゆとりができて、大抵の不満が解決されて心に余裕ができるから人にも優しくできたりするという感じでしょうか。
でも、私はこうも思いました。
着る物もあって、ご飯を食べて、ゆっくり眠れる。
こういう当たり前な生活に幸せを感じることができれば、裕福さに関わらず心にゆとりができて、人にも優しくすることができるんだって。
お金をいっぱい持っていたことは私にはありませんが、持っているから幸せというわけではないでしょう。
銀行の貸金庫から盗んでいた人だって、給料は私の何倍も貰っていたはず。
結局持っているお金の金額だけ生活水準も上がってしまって、欲望はどんどん膨れ上がっていくのでしょう、人間ってそういうものです。
今ある生活をどう楽しむか、どう幸せであるかを考えて過ごす方が、よほど素敵な人生だと思います。
そうやって生きている人こそが、礼節を知った人なのではないでしょうか。
縁の下の力持ち

人の知らないところで他人のために力を尽くすこと、またその人。
こういう人が一生懸命に頑張ってくれているから、世の中は上手く回っているのだと感じますよね。
身近なところでは、家で家事を頑張ってくれている人だと思います。
家事をしてくれていることは知っていても、その大変さや苦労は知らない人の方が多いでしょう。
でもそれを頑張ってくれている誰かがいるから、綺麗な家に住めて、清潔な服を着れて、美味しいご飯を食べられて、安心して眠ることができるのです。
当たり前なんかじゃないですよ、当たり前だと思ったらダメです。
今頑張ってくれているその人がもう嫌だと感じてしまったら、あっという間に日常は崩れるのですから。
きちんと感謝を伝えること、労うことを忘れてはいけませんね。
親の心子知らず

親の深い心も知らずに、子どもは勝手気ままにふるまうということ。
ですが逆もまた真なり、お互いの気持ちは話してみないと伝わらないものです。
親になるとどうしても今までの経験から、子供には最短を歩ませたいだとか、失敗するのも経験だとか、そういった自分の考えを押し付けがちになってしまうので。
子供だって考えがあって、気持ちがあることをきちんと意識してあげられるかどうか、それが親としての力の見せどころな気がします。
でも子供だってね、もう少し親が言っていることの意味を考えてみてください。
親になると自然とわかることですが、子供を貶めようとして助言する親はいません。
言葉をかけるということは、それには意味があるのです。
親の考えが全てではないですが、そこには一つの答えが隠れているんですよ。
それを読み取ろうとせず、自分のことを解ってないと断じるのは早計です。
これは親子だけの話ではなく、誰が相手でも言えることではないでしょうか。
理解できないのはお互い様、意見を押しつけるのではなく、言葉を交わすことでその溝は埋まっていきます。
関わることを止めないで、歩み寄ってみる第一歩を踏み出してみてください。
雲の上はいつも晴れ

どんなに辛いことも、いつかは終わるということ。
雲の上はいつだって晴れていることから、どれほどの嵐であってもその向こうに行ってしまえば晴れ。
今は辛いことが多いかもしれませんが、それでも永遠に続く嵐はありません。
雲の向こうを目指すように、進んでいれば晴れるのです。
嵐を一緒に乗り越えてくれる人がいれば、もっと心強いですね。
案ずるより生むが易し

難しそうに思えることも、やってみると案外簡単だったりすること。
何かを始める前って色々と調べたりして、そういった情報が多いほどに難しそうに見えてしまいますよね。
でもまずは始めてみること、始めてみればその不安は杞憂だったとわかることも多いです。
やってみたことは経験として無駄にはなりませんし、もし失敗してもそこから学べることはたくさんあると思います。
動画や写真、文字で得られる情報にはやっぱり限りがあって、編集された一部でしかありません。
実際に見て、感じる、体験すること以上に情報を得られることはないのです。
恐れるよりも、まずは一歩から。
調べるよりも先に始めてしまう方が、難しく考えなくていいのかもしれませんね。
高きに登るには卑きよりす

物事を成功させるには、まず身近なところから始めて一歩一歩堅実に順序を踏んで行わなければいけないという教え。
最初から大成功することはありません、一生懸命に頑張った人にこそ成功が待っているということですね。
メジャーリーグで大活躍している大谷選手だって、努力を続けたから英光を手にすることができたのだと思います。
今はまだその努力が報われないと感じていても、続けることでいつか辿り着ける場所があると思います。
何かをずっと続けることは大変ですが、積み重ねることは本当に大切です。
私のこのブログも、積み重ねていった先に何かを得られるかもしれませんから、頑張って続けていこうと思っていますよ。
湯を沸かして水にする

せっかくの苦労を無駄にしてしまうこと。
なんというか、そのままのことをよくやってしまいます。
コーヒーを飲もうとして湯沸ポットのスイッチを入れたのに忘れて、数時間後に思い出してまた沸かし直す、まさにことわざのまんま。
しかも何度やっても学習しない、失敗から学ばないお馬鹿さんなのです。
ある意味では一番共感できたことわざだと思います、皆さんは経験ありませんか?
このことわざを見かけた瞬間に苦笑いしてしまいました、これ私のことだって。
沸かしている間に別のことを始めてしまうから忘れるんですよね、気をつけないと。
感想
流石に5万ものことわざの全てを見たわけではありませんが、本当にたくさんのことわざを見ることができて楽しかったです。
似たような言葉もたくさんありましたし、紹介した他にもたくさん的を射てると思えるものはありました。
ことわざの表現って、文章を書く人からすると素敵な比喩が多くて勉強になります。
多くの失敗や成功がこうして後世に残され、我々の人生においても教訓となって生きている。
これからも増えていくでしょうから、時代に則したことわざも生まれてくるのでしょうね。
それってあなたの感想ですよね
論点から外れた相手を論破するさま。
みたいな感じで。
ことわざは過去の教訓ですから、数百年経った頃にはあなたの言葉もことわざになっているかもしれません。
それでは今回はこのあたりで。
あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。
Radiotalkで音声配信もしていますので、興味がある方はぜひこちらも聴いてみてくださいね。
番組 #真也のFeelingNight #Radiotalk https://radiotalk.jp/program/155656
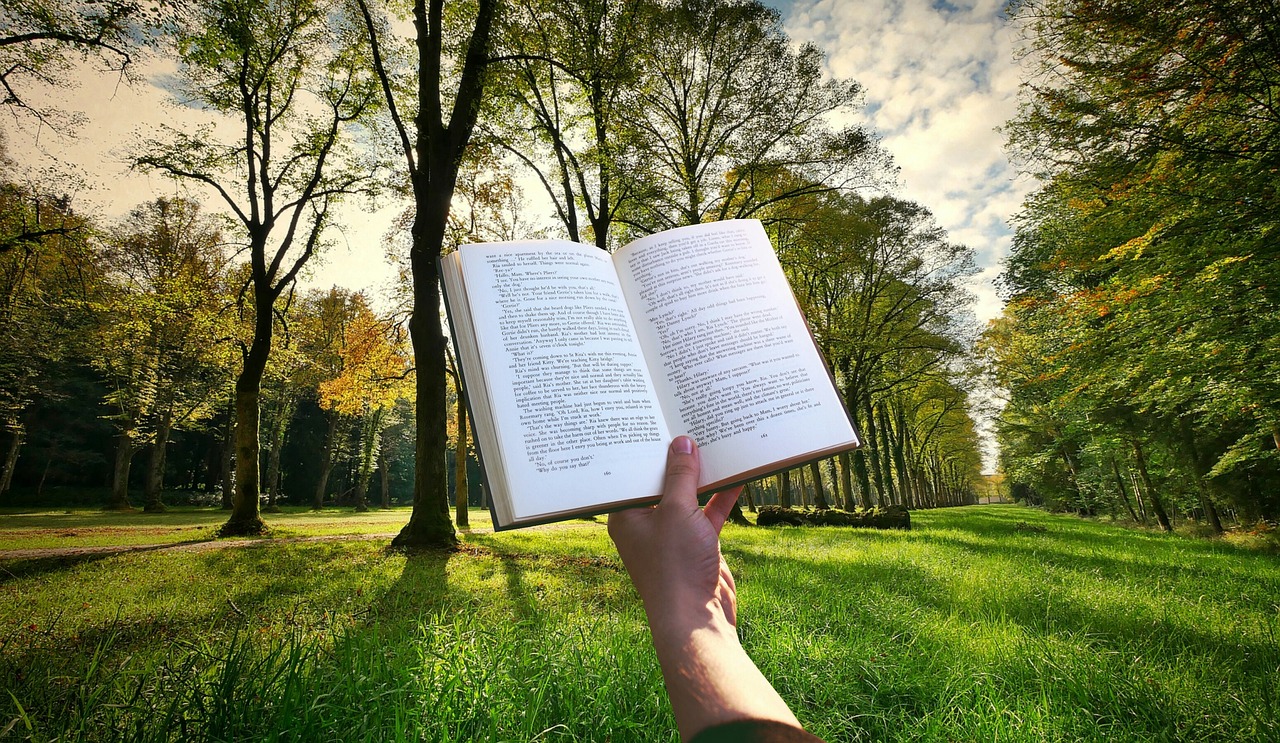


コメント