こんにちは、桐生真也です。
テレビで受験シーズンの話題が取り上げられていて、一生懸命に頑張る受験生達の努力が放送されていました。
もう随分と昔の話ですが、私は一生懸命勉強するのが嫌でAO入試に逃げたなぁとか思ったり。
最難関四大大学とか、頭の仕組みから違うんじゃないかと馬鹿なことを考えていましたよ。
そういえば、何でも四つにするの好きですよね。
四天王とか、四皇とか、四大貴族とか。
気になる!
何か理由があって4つを選んでるのか?
4つだと都合がいいことがあるのかな?
気になると止まらないです、調べてみましょう。
浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。
気ままにお付き合いいただけたら幸いです。
身の回りにある”4”という数字
”死”を連想させる4

日本では昔から4という数字は忌み数として扱ってきた風潮があります。
読み方が”死”と同じであるからという理由ではありますが、病院やホテルでは4号室が飛ばされていたりしますね。
私も昔見たことがあります、4号室だけ飛ばされて5号室になるんです。
子供心に不思議に思っていましたが、親に理由を聞いて妙に納得した覚えがあります。
こういった風潮は日本だけではなくアジア圏では多く見られるようで、漢字を使う中国でも同じように嫌がられる数字とのことです。
4階が存在しない建物だとか、4の代わりにF(four)を使っていたりとか。
日本でも車のナンバープレートでは、「42」と「49」は使ってはならないとして欠番になっています。
それぞれ「死に」と「死苦」になってしまうのが理由だそうですから、法律に影響するほどに根深い風潮だと言えますね。
海外では悪魔を意味する「666」という数字が嫌われるようで、宗教なども関係する文化的違いとなっています。
最近はそこまで意識されているとは感じなくなりましたが、いまだに病院などでは4階に手術室を作らないといった配慮はなされているそうですね。
どうしても嫌なイメージを持ってしまいがちな4という数字ですが、むしろ優れている点が多くあるのです。
”四角形”の安定性
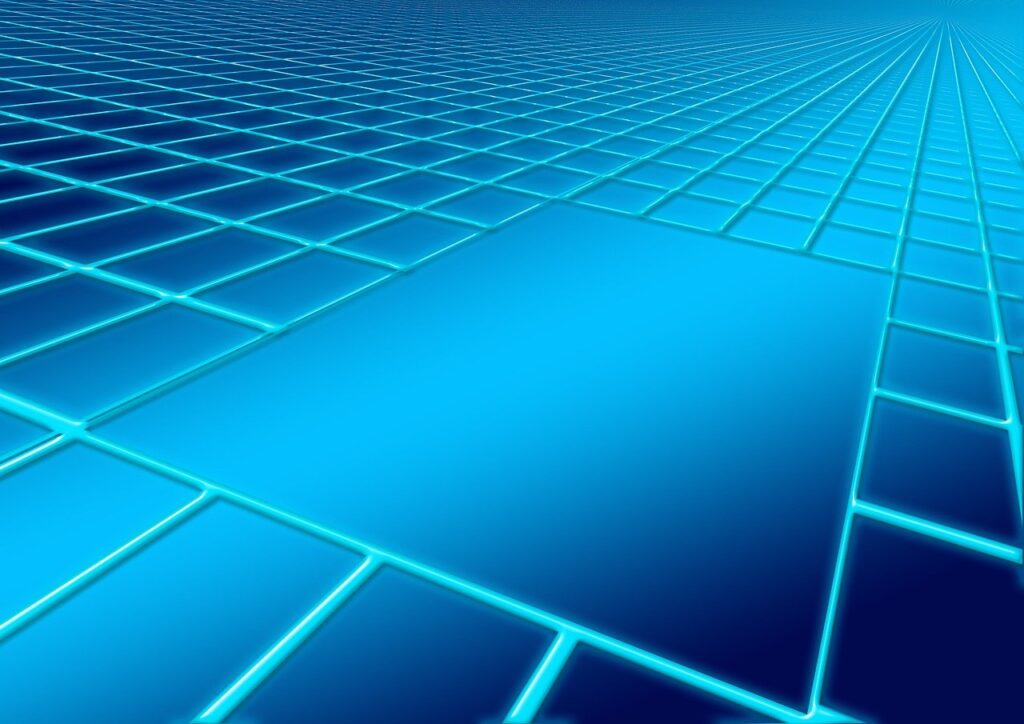
形として、”四”角形とは非常に優れていて安定している形と言えます。
特殊な場合を除けば、我々の住む家の土台は四角形で作られています。
テーブルや車のタイヤも、4つの面で支えています。
動物も四足歩行ですよね、生物的にも四点で支えるということは最適だと示されています。
四角形は転がることもなく安定していて、組み合わせた際にも同じく四角形になりますし、積み重ねることも容易です。
古代エジプトのピラミッドや、昔ながらのレンガなども四角形に作られたものを積み重ねたものですね。
何千年もそのまま残っているあたり、安定性の高さを歴史が証明してくれています。
デザインとしても四角形は均一性があり、シンプルですっきりとしたイメージを感じさせるものが多いですよね。
視認性も高く、強固なイメージもあるため、様々な場面でデザインとしても利便性が高いそうです。
四角形の物を挙げ始めるとキリがないほどに、私たちの周りには四角形が溢れていますから、その安定性の高さは確実なものと言えるでしょう。
数としての”4”

4つに分けるということは、脳が理解がしやすい数ということが解っています。
人間の脳は多くの情報を同時に処理するのが難しいとされていますが、その情報を4つのカテゴリーに分けることで一つのまとまりとして整理し、認知的負荷を軽減することで理解しやすくなるようです。
仕事などでよく言われる”PDCAサイクル”も、仕事を4つの段階に分けて行うという考え方です。
日本でも物語の組み立て方として”起承転結”という言葉もありますし、これ自体も四字熟語ですね。
四分割にすることでバランスがよく、また見た目にも直感的に理解がしやすいために昔から多用されてきました。
東西南北や四季などもそうですが、分布図なども十字に区切られて四分割となっていますね。
心理的にも四分割されているのは安心するのだそうです。
選択肢が十個あったら多すぎるし、二つでは少なすぎる、四つならち丁度いいという感じでしょうか。
最近私が見た四分割は、ハッピーセットのおもちゃの選択肢でした。
確かにこれが二種類しか選べなかったら男女で分けるだけって感じですし、逆に六種類とかあってもどれを選べばいいか迷ってしまいそうですね。
四種類という数が、自由に選べて丁度いい選択肢なのかもしれません。
選ばされたとも感じないですよね、心理的に安心するというのもわかります。
学校での班決めも四人一組だったり、私が入社した時の研修グループも四人一組でしたね。
人数として把握しやすく、合同となっても管理しやすいのが理由でしょう。
無意識的に4つに分けたり、4つでひとまとまりとすることは、思い返してみるとよくありますね。
ジョハリの窓

こういった四分割は様々な分野でも使われていて、調べてみた中でも実生活で使えそうだと感銘を受けたのが、この“ジョハリの窓”という自己分析の手法です。
ジョハリの窓とは、1955年に心理学者のジョセフ・ルフト氏とハリントン・インガム氏によって考案された概念で、自己分析と能力開発に効果が高いとされている手法です。
自分自身を分析する為に、自分の特性を、自分から見た項目と他人から見た項目を組み合わせ、以下の”4つの窓”に分類していくというものです。
- 開放の窓(自分も他人も当てはまると感じる)
- 秘密の窓(自分は知っているが他人は知らない)
- 盲点の窓(自分はそう感じないが他人は当てはまると感じる)
- 未知の窓(自分も他人も当てはまらないと感じる)
この未知の窓に含まれる項目を訓練したり学習することで、能力開発に繋がっていくという考え方です。
非常に面白いと感じましたし、四分割されていて理解もしやすい内容だと感じました。
自分には見えていない自分を直感的に知ることができ、自分には何が足りていないのか理解しやすくなりますね。
項目は事前に用意したものからそれぞれが選んでいく方式なので、状況に特化した項目を作ることで応用性も高いなと思います。
例えば家事を項目に選んでいって、自分ではやっていると思っている家事と、家族はやっていると思っていない家事を選んでもらって、やれてない部分を頑張って手伝うようにするとか。
ただし注意すべきは、少なからず自分の内面も曝け出す必要がありますし、隠し事があっては意味がありません。
自分の内面も偏見なく見てくれる相手でなければ成り立たない部分もありますので、安易に強要しないようにしてください。
家族でやってるやってない論争を繰り広げるとか、後が怖すぎるので。
自分自身をカテゴリー分けされることに嫌悪感を示す人もいますので、お互いに同意の上で行うようにしてくださいね。
こういったことは前向きに議論するからいいのであって、争いの種になってはいけませんから。
感想

4という数字の便利さを知ることができて非常に有意義でした。
普段は無意識に使っている分け方や選び方にも、本能的に感じるわかりやすさがあったのでしょうね。
なんとなく日本人として避けたがってしまうのは、数字や言葉に意味を当てはめてしまう文化の影響が強いようです。
四つ葉のクローバーみたいに、幸せの”し”だって思えばいいじゃないですか。
悪い意味じゃなく、いい意味で捉えていくのが大事なのではないかと思うのです。
漫画とかで四天王が出てくるとワクワクしますしね。
何か難しいことに取り組むとき、これからは四分割して考えてみたらすんなりできるようになるかもしれません。
様々な場面で活用できる4という数字。
意識してみることで、便利になることもたくさんあるかもしれませんね。
それでは今回はこのあたりで。
あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。
Radiotalkで音声配信もしていますので、興味がある方はぜひこちらも聴いてみてくださいね。
番組 #真也のFeelingNight #Radiotalk https://radiotalk.jp/program/155656



コメント