こんにちは、桐生真也です。
今年ももう残すところあと少し、季節のイベントがたくさんな時期になってきました。
クリスマスやお正月、テレビでは競馬の有馬記念のCMがこの時期になると放送していますね。
学生は冬休みに入り、お仕事を頑張っている皆さんもそろそろ仕事納めでしょうか。
残念ながら警備員には関係ありません、三箇日もしっかりとお仕事でございます。(泣
さて前置きが長くなりましたが、今回は”宝くじ”について調べていこうと思います。
誰もが知っている宝くじ、一等が当たれば夢のような金額がお手元に。
毎年年末になると宝くじ売り場に行列ができていたりしますが、そもそも宝くじとはいつ頃から始まったものなのか。
当たったらどうなるの?どれくらい手元に残るの?
気になる!
当たることがあるかどうかは別として、気になってしまいました。
まさに捕らぬ狸の皮算用とはこのこと、しかし誰しも夢や妄想をする権利くらいはあるのです、憲法でも保障されています。
浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。
気ままにお付き合いいただけたら幸いです。
宝くじっていつ頃から始まったのか?その遍歴

古くは江戸時代初期、寛永元年(1624年)頃にまで遡るそうです。
現在の大阪府にあたる摂津国の箕面山瀧安寺。
そこでは正月の元旦から7日までに参詣した善男善女に名前を書かせた札を木札を唐びつに入れ、寺僧がキリで3回突き、3人の”当せん者”を選びだし、福運の御守りを授けたことが始まりとされているそうです。
…なんだか難しい言葉がいくつか出てきたので、その説明もしていきますね。
善男善女とは仏教用語の一つで、「信仰心が篤く、徳の高い人々」を指す言葉のようです。唐びつとは中国を起源に持つ美しい装飾を施された道具箱のことらしいですね。
徳も高くて運も良くて、何だか聖人のようですね。
イメージとしては、箱に手を突っ込んでくじを引く感じに似てるでしょうか、キリを突き刺すのはまたパワフルな感じもしてしまいますが。折角の綺麗な箱に穴も開いてしまって勿体ないような…。
この当時は現代のようなお金をやり取りする宝くじではなく、お正月の祭事のような雰囲気だったのでしょう。
己の信じる心が仏様に届いたんだ、そう実感することができるなんて夢のようです。夢が叶うという意味では現代の宝くじと同じですね。
では現代のような宝くじの形式になったのはいつ頃からなのでしょうか。
箕面山瀧安寺を始まりとして、こういったくじに金銭を結び付けて市井に広がっていきました。現代で言う宝くじの原型”富くじ”が広がったのです。
しかしながらあまりにも広がってしまったため、徳川幕府は元禄5年(1692年)に禁止令を発令。以降は神社にのみ修繕費用に充てるための富くじ発行を許すのみとなり、それらは天下御免の富くじとして”御免富”と呼ばれるようになります。ですがそれも天保13年(1842年)の天保の改革によって禁じられてしまいます。
この富くじが現代の宝くじの原型となったようです。
やっぱりこういうくじというのは、いつの時代でもワクワクするというか、楽しいものなのですね。
当たるかもしれないという楽しみは、老若男女問わず多くの人が感じることだと思います。
しかし、市井に広がりすぎて禁止令とか、あちこちで好き勝手に富くじが発行されていたのでしょうか。
中には集めたお金を返さずに運営者が逃げるといったトラブルもあったことでしょう。
誰々さんが発行した富くじは当せん額も大きいし信用できるが、あそこの富くじは当たりがなかったらしいよ、とか。
幕府が禁止するほど制御できない市場に広がってしまったとも考えられますね。
こういったこともあり、その後富くじは100年以上も発行されることがなく、一時的に歴史から姿を消していました。
しかし、昭和20年(1945年)の7月、第二次世界大戦の終戦間際の頃。
軍事費用充填の為に政府が発行した”勝ち籤”、一口10円で当たれば一等10万円の富くじを発行しましたが、その後すぐに終戦となりました。
現代の貨幣価値に換算すると、終戦間際ということもあり価値が大きく変わるそうなのですが、おおよそ10倍~20倍くらいらしいので、100円が100万円になるかもしれないとった感じでしょう。
この勝ち籤が発行されて以降、各自治体などで復興資金調達の名目で富くじが発行されるようになり、全国的に広がっていきました。
そうしてはじめは100万円ほどだった一等の金額も徐々に増えていき、1979年には皆さんも名前を知っているサマージャンボ宝くじ・ドリームジャンボ宝くじ・年末ジャンボ宝くじといったジャンボ宝くじが始まりました。
現在では前後賞含めて10億円とか、とんでもない数字になってきていますね。
夢がありますよね、当たったら何を買おうとか妄想で盛り上がったことがある人も多いかと思います。
私なんかは田舎に家を買って、車も買って、生活基盤を整えたら死ぬまでのんびり過ごしたいとか考えちゃいますね。
贅沢をしたいとかではなく、安心して過ごしたいという気持ちの方が強いです。
皆さんはどうでしょう、どんな夢を思い描きますか?
私と同じようなことだったり、最近ではまとめて投資に回したりする人も多そうですね。
いっそ豪華にあちこち旅行したり、美味しい物をたくさん食べて回ったり、できることはいっぱいありますからね。
まさに夢を買うといった感じなのですが、さてその当せん確率はどれほどのものなのでしょう。
当せん確率はどれくらいなのか?当せんした後の動き
調べてみたところ、発行されるくじの枚数で変動するので必ずというわけではないですが、以下のような確率になるみたいです。
- 1等 1000万分の1
- 前後賞 500万分の1
- 2等 1000万分の3
- 3等 10万分の1
- 組違い賞・4等 1000万分の1099
- 5等 100分の1
- 6等 10分の1
年末ジャンボ宝くじだけは更に確率が下がって、2000万分の1となっていくようです。
いやぁ、当たらないですよねこれは。
しかしそれでも夢を見てしまうあたり、宝くじには大きな魅力がありますね。
ちなみに調べてみたら、雷に打たれる確率が1000万分の1だそうです、その倍も確率が低いって…。
よく買わなきゃ当たらないんだよって言う人がいますし、私自身もそう言いながら買うのですが、こうして調べてみるとどうしようもなくお金をドブに捨てている気分になってしまいます。
もちろん宝くじ自体の魅力はこの先も衰えないと思いますし、否定するつもりもまったくありませんが、素直に購入するお金を使って子供に何かを買ってあげるほうが賢明な気がしてきました。
世界人口は現在81億人ちょっといるそうなのですが、計算したら410人くらいしか当せんしません。
雷に打たれたってニュースすら普段から聞かないのですから、これがいかに低い確率なのかを実感してしまいますね。
もちろん買った枚数が多いほどに分子は増えていくので確率は上がります……上がりますけどね。
多くの人は10枚セットで購入すると思うので、単純計算では200万分の1ですが、それでも当たるとは思えない数字ですね。
ちなみに、アメリカで過去に出た当せん最高金額は20億4000万ドル、日本円にして約2,970億円とのこと。
6つの数字の組み合わせを選んで購入する宝くじらしいのですが、当せんする確率はなんと驚愕の2億9220万分の1。
流石はビッグアメリカ、宝くじ一つとっても規模が桁違いすぎる。
何ヶ月か当せん者が現れなかった結果キャリーオーバーを繰り返し、このような莫大な金額に膨れ上がったとのこと。
ちなみにキャリーオーバーとは、当せん者不在のお金を次回の抽選に繰り越していく仕組みのことらしいです、これも私は知らなかった。
日本のキャリーオーバーは流石にオーバーした分の全乗せはされないようです、キャリーオーバー分の一部が上乗せされるみたいですね。
だからここまでの金額にはならないと思われます、ちょっとケチだなとか思ってしまったことは秘密です。
さて、これほどの低確率を潜り抜け、見事当せんした場合はどうなるのでしょう。
- 1万円以下の場合、各宝くじ売り場や、銀行で受け取れる。
- 1万円以上~10万円の場合、特定の宝くじ売り場や、銀行で受け取れる。
- 50万円~100万円の場合、銀行にて本人確認が必要。
- 100万円以上の場合、初めに最大で100万円受け取れるが、残りには手続きが必要なため受け取りに時間がかかる。
流石に全額一度に貰えることはないようです、額が大きいですからね。
ちなみにここで言う銀行とは”みずほ銀行”のこと。
一部の例外を除いて、宝くじのほとんどはみずほ銀行にて管理しています。
先程説明した〇〇ジャンボ系は全てみずほ銀行にて受け取れますが、ゆうちょ銀行などで販売している宝くじもありますので、当せんした際にはどこで販売しているか調べてみる必要がありますね。
最近ではインターネットでも購入できますし、受け取りの際も本人確認が済んでいる場合は口座振込されますし、窓口で当せんしたか確認する必要もないので受け取り忘れもありません。
受け取り忘れは結構多いようで、令和4年の記録だとじつに99億円分もあったそうです。
窓口で当たるかどうかのワクワクを楽しみたいんだ!
そういった楽しみ方もあるとは思いますが、受け取り忘れは避けたいという方はインターネット購入がオススメです。
みずほ銀行の口座をお持ちの方は、残高照会のページからも購入できますし、口座から購入額を直接引き落とされますので便利ですよ、私はこちらで購入しています。
当せんしたお金は後日きちんと”タカラクジトウセンキン”って名前で加算されますので安心で楽です。
これから先で購入を考えている方は、検討してみては如何でしょうか。
宝くじの当せん金って税金かかるの?
さて、気になるといえばもう一つ、当せんしたお金に税金はかかるのか。
ご安心下さい、宝くじは非課税です。
これは法律でも決まっていることで、当せん金付証票法という法律で非課税とされています。
なので、何億円も当たったとしても、全部丸ごと受け取れます、ここが宝くじの嬉しいところ。
競馬などのギャンブルでは20万円以上の利益を出してしまうと、確定申告や税金の支払いが必要なのに対して、宝くじにはそれがありません。
当たった夢の金額を国に削られて落ち込むこともないのです。
仮に税金の支払いが必要だったとするならば、所得税は総所得の金額によって税率が変わりますが、例えば1億円当たった場合は実に45%も所得税が発生するので、それだけで半分近く持っていかれます。
錬金術の禁忌を犯したよりも持っていかれてて、正直ドン引きしました。これだけで手足どころか下半身全部ですよ。
そこから更に住民税の支払いもあり、10%減りますので、手元には4,950万円程しか残りません、何て恐ろしい。
流石にこの法律が変わることはないと信じたいですが、今後財政悪化した政府が目を付ける可能性もないとは言い切れない市場規模ですからね。
最近の税金の上がり方から考えると、そう遠くない未来で可決されてしまうかもしれません。
そうならないように祈るばかりです、そうなったら購入する人も減るでしょうね。
感想
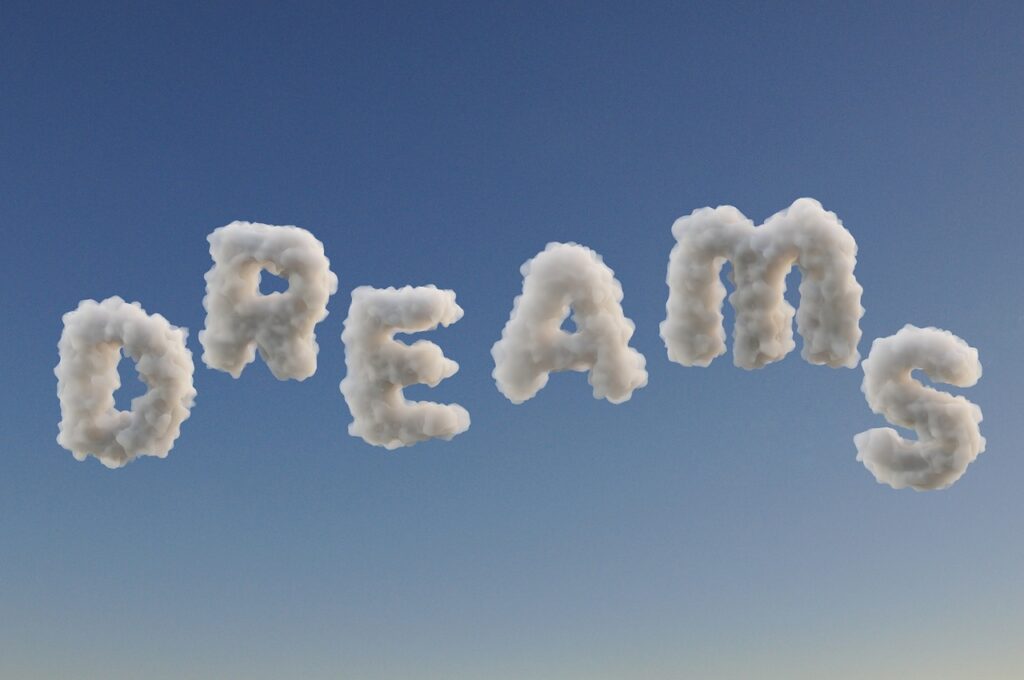
宝くじ。
始まりは神社の祭事から、国の財源確保を経由して今に至る。
知らないことばかりで驚きました。
そして江戸時代の人達も、現代と同じく夢を描いていたのだと。
当たるかどうかはともかく、やっぱり夢があることに間違いはないようです。
ですが調べるほどに当せん確率というのが恐ろしく低いものだと実感しましたし、これを是とするかの賛否は分かれそうですね。
ですが正解か不正解か、そういった枠組みで測るものではないと思います。
私は夏と年末だけ少し購入するだけですし、当たったことがあるのも1万円が最高です。
6,000円分購入していたので、4,600円増えたことになりますが、翌年の購入で消し飛びました。(笑)
それでも買ってからは当たることをお祈りしながらワクワクしていますし、妄想していたことが現実になるなら最高ですよね。
くじ引きって、どんなものでも楽しいじゃないですか。
お正月の御神籤や、縁日で紐を引っ張るくじ。
どれも景品自体は高価なものではないかもしれません、正直確率を考えてしまったら割に合わないことの方が多いです。
ですがそこには確かにワクワクやドキドキがあり、値段以上の価値があると思うのです。
色んなくじに根付いている思いは、”当たるかもしれないワクワクを買う“というところにあるのではないでしょうか。
それでは今回はこのあたりで。
読んでいただきありがとうございました。



コメント