こんにちは、桐生真也です。
梅雨がもう少ししたら来てしまうのかと、最近ちょっと憂鬱です。
私は変な癖毛なので、湿気が多くなると毛先だけどんどん上を向いてしまうように。
嫌だな、雨だと外出もし辛いし、雨をのんびりと楽しめるような生活でもないし。
ところで、最近子供がぬりえをしている姿を見て、ふと思ったのです。
鉛筆っていつ頃からあるんだろうな。
気になる!
小学生の頃は鉛筆しか使っちゃダメって言われてたなとか、バトルエンピツって流行ってたなとか。
なんとなく昔を懐かしみながら調べてみました。
浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。
気ままにお付き合いいただけたら幸いです。
鉛筆が作られたのは16世紀頃

鉛筆が初めて記録として登場するのは16世紀の半ば頃。
スイスの博物学者であるコンラート・ゲスナーが使用していたとされるものが、一番古い鉛筆の記録となっているようです。
現代の鉛筆に近いものが生産されるようになったのは、17世紀初頭のイギリス。
その当時は筒の先に黒鉛(鉛筆の芯になる炭素鉱石)を入れる仕組みで、無くなったら新しいものを補充する構造だったが、黒鉛を木の板で挟んで削る構造のものも1616年頃には発明されている。
鉛筆が開発されるまでは万年筆のようにインク瓶を持ち歩かなければならなかったりと、携行性においては不便であったと思われます。
ちなみに消しゴムはもっと後になるまで発明されておらず、1770年まではパンを使って消していたそうです。
美術の授業でパンを使って消しているシーンをアニメとかで見たことありますね、間違ってそのまま食べちゃってましたけど。
芯になる黒鉛が産出されている間はイギリスが鉛筆の輸出大国でしたが、19世紀頃には黒鉛が掘り尽くされてしまい、以降は中国やブラジルなどから産出された黒鉛が使用されるようになったそうです。
黒鉛が勿体ないからということで、鉛筆の頭の方にはそもそも芯を入れないという工夫をして節約したりしていたようですね。
この工夫は現代でもやってもいいかと思いますけどね、どうせ最後の方は短くなりすぎて持てなくなってしまいますし、そこには芯は不要でしょうから。
そしてオーストリアでは黒鉛不足を解消するために黒鉛と粘土を混ぜて作った芯を開発し、この技術が現代の鉛筆でも使用されているそうです。(合成黒鉛)
黒鉛の粉まで使うことができ、粘土の割合で濃淡も調整できるものですね。
この技術によってかなり安価で鉛筆を製造できるようになり、開発者であるニコラ=ジャック・コンテさんは博覧会で賞を受賞したとか。
鉱石そのものを使うよりも加工もしやすいでしょうから形や長さも自由にできますし、何よりも無駄が少ないですよね、とってもエコ。
鉛筆の形については当初四角形が主であり、それも長い期間そのままでした。
1889年にオーストリアのKoh-i-Noor Hardtmuth社が発表した、六角形で合成黒鉛を使用した鉛筆が非常に安価で好評となり、以降の鉛筆の基本形となったそうです。
その形に落ち着くまでの間には、芯が四角形だったり、軸が八角形だったりもしたそうで、多くの試行錯誤があったのでしょう。
ちなみにですが、黒い鉛筆は六角形ですが、色鉛筆は角がなく丸いですよね。
これは芯の硬さが関係しているそうで、色鉛筆の芯は合成黒鉛より柔らかく折れやすいので、丸い軸にすることで外部からの力が均等に伝わり、折れづらいようにしているそうです。
確かに色鉛筆の芯って折れやすい印象ありますね、私の筆圧が強すぎただけではなかったのですね。
他にも受験生用に、合格にちなんで五角鉛筆なんてのもあるみたいです、本当にこういうゲン担ぎが好きですね日本人。
日本における鉛筆
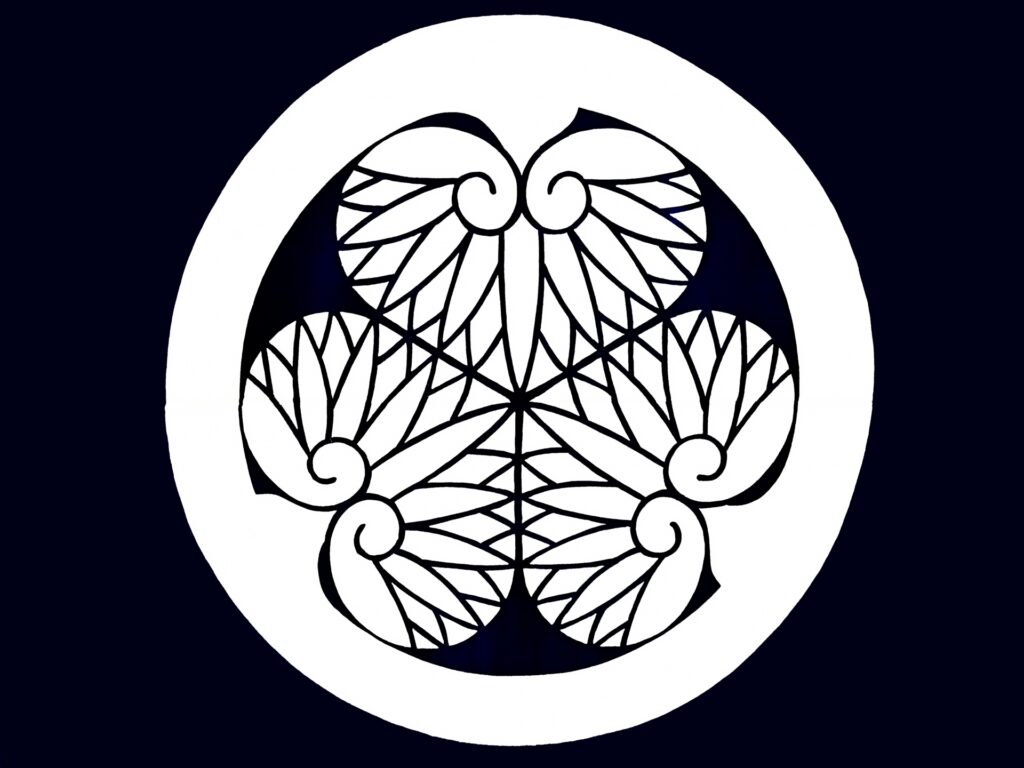
日本では徳川家康や伊達政宗が鉛筆を持っていたようで、今も資料として現存しているそうです。どちらも輸入品であるとのことですが。
日本での鉛筆製造は、1874年にオーストリアのウィーンから政府伝修生が持ち帰った鉛筆製造技術を元に小池卯八郎という人物が鉛筆製造を開始、以降製造会社がいくつか作られました。
真崎鉛筆製造所(現在の三菱鉛筆)はその当時から続く老舗で、まだ鉛筆が浸透していなかった日本において逓信省(現:総務省)御用品として「局用鉛筆」が採用され、現在も新しい商品を世に送り出していますね。
Uniの鉛筆やサインペンなどを見たことがないという人は多くはないでしょう、そんなに昔からある企業だったのが驚きです。
あとはトンボ鉛筆などでしょうか、トンボのマークがついた鉛筆は使っていた気がします、MONO消しゴムは一度は使ったことがある消しやすい消しゴム、何度もお世話になりました。
しかし残念ながらコンピューターの普及や少子高齢化による学生の減少、シャーペンの利用が多くなっていることから、鉛筆の需要は年々減ってきているようです。
流石に現代ではまだ鉛筆を使ったことがないという人はほとんどいないかと思いますが、いつかはそういう時代になってしまうのでしょうね。
鉛筆削りでゴリゴリして、尖った芯で書き始める楽しさが失われてしまうのは残念なような寂しいような。
おまけ
写真を載せられないのが残念ですが、私が小学生の頃にはバトルエンピツなんてものが流行った時期があったんですよ。
ドラゴンクエストのモンスターやキャラクターがプリントされていて、六角形の各面に技のダメージとかが書いてあって、転がして出た面の効果で相手のHPを削りきった方が勝ちというルールでした。
追加でキャップを装備して効果を増やしたり、かなり色々な種類が販売されていたと思います。
まぁあまりに学校で遊ぶもんだから禁止になってしまったのですが。
楽しかったですよ、授業の間の休み時間には結構遊んでいましたから。
もちろん削るなんてもったいないから鉛筆としては全く使わないので、存在意義としてはややおかしい気もしますが。
他にも鉛筆について調べていたらすごいものが出てきました。
その名も「パーフェクトペンシル」、名前からしてもう強気。
ドイツで1761年に創業され、現代まで続く鉛筆の長さや太さなどの基準を作り、現在も世界的な文具メーカーとして名高いファーバーカステル社が販売しています。
その鉛筆のお値段、Amazonで調べたら安くても31,355円しました、強気すぎる値段設定。
”パーフェクトペンシル”で調べると出てきます、プラチナコーティングとか書いてあるやつですね。
鉛筆本体にクリップ付きのキャップや消しゴム、鉛筆削りまで全部一つにまとまっているパーフェクトな鉛筆です。
キャップなどの金属部分は真鍮製らしく、表面はプラチナコーティング。
鉛筆本体の替えも、1本約7,000円。
公式サイトを見てみたら、プロジェクト・ステラ・エディションなるものが1,000本限定で販売されるようです、値段は書いてなかったですが。
デザインは確かにカッコいいです、専用の豪華な箱にペン立てまで付いてくる、気になる方は公式サイトを見てみて下さいね。パーフェクトペンシル
どんな物でもとてつもなく高級な物ってあるんですね、鉛筆なのにAmazonだと対象年齢:成年って書いてあって笑ってしまいました、そりゃこんな高い鉛筆小学生には使わせないでしょうね。
感想

私にとって鉛筆って、文字を初めてちゃんと書いた道具で、近頃はシャーペンすら使わなくなったけど、時々鉛筆で文字を書きたくなるような時があります。
ボールペンとかよりも柔らかいというか、なんとなくですが温かみを感じるというか。
書いている内に芯が丸くなってしまって、段々と文字も太くなったり書きづらくなったりで、実用性に優れているかと言われると素直に頷けないけれど、少しだけ削って書き始めるのはやっぱり楽しい気分になっていました。
削るのが楽しくて、削りすぎてどんどん短くもなっていましたが。
小学生の頃しか使ってないのに、いつか無くなってしまうのだとしたら寂しい。
鉛筆を使った記憶は、懐かしく楽しい思い出なのではないかと思います。
それにしてもパーフェクトペンシル、ちょっとやりすぎですよ。
それでは今回はこのあたりで。
あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。



コメント