こんにちは、桐生真也です。
何となく陽が落ちるのが遅くなってきて、まだまだ寒い日が続きますが春も近づいてきてるのかなと感じます。
そしてこのところ、あちこちのコンビニなどで”恵方巻”の予約開始ですという広告を目にしますね。
そうだ節分だものなぁと思いつつ、値段を二度見して苦笑い。
年々豪華になっていませんかね、中身も値段も。
それと節分と言えば”豆まき”ですよね、「鬼は外、福は内」ってやつです。
こう連鎖的に色々と思い浮かべていると、気になる!ってなってくるのです。
子供の頃は保育園で豆まきをしたなとか、家の中で派手に豆を投げたせいで掃除が大変だったり。
気になってしまうのはとってもいい機会です、せっかくなので調べてみましょう。
浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。
気ままにお付き合いいただけたら幸いです。
節分とは季節の変わり目の前日を指す日
節分は必ずしも2月3日ではない

節分とは「季節を分ける」という意味を持ち、立春~立冬となる日の”前日”のことです。江戸時代以降は立春の前日を特に節分とするようになった。ほとんど場合は2月3日であるものの、閏年の翌年は日付がずれるため、2025年は2月2日が節分となる。
前回は2021年の節分が2月2日だったようですが、まったく覚えていませんね。
閏年が関わるだなんて思ってもいませんでした、2月3日生まれの人に対して節分の生まれなんだねと昔から言ってしまっていましたし。
調べなければ日付を間違えてしまうところです。
春を迎える前の伝統行事なわけですから、間違えてしまうと意味がないですしね。
立春という言葉も聞いたことはあったものの意味は曖昧だったのですが、立春とはまさに春の訪れを感じ始める頃で、九州の方では梅の開花時期となったり、この日以降に南寄りの風が吹くと”春一番”と呼ばれるそうです。
とはいえまだまだ寒い日が続く時期でもありますが、節分の翌日から春とする基準もあるようです。
豆まきは”魔滅まき”

節分に豆まきをするようになったのは平安時代の頃。中国から伝わって来た”追儺”という行事が元になっています。大晦日に邪気を払う意味で行われていたもので、季節の変わり目には邪気が溜まるという考えから、節分の日に宮中で執り行われていました。
一般にも広がったのは室町時代の少し前(南北朝時代)、寺などを中心に執り行われていた。
古くは疫病などの悪いことは鬼の仕業であるという考え方があった。対して穀物には生命力や魔除けの力があるという信仰があり、”まめ”が転じて”魔目”となり、鬼の目にぶつけて魔を滅するで”魔滅”という意味で豆まきが行われる。
何だか漫画とかの必殺技みたいな語呂合わせで面白いですよね、それこそ鬼滅の刃とかに出てきそうな。
魔を滅する、つまり無病息災を祈っての行事とのことです。
日本人は昔から言霊という考え方があるので、当て字が大好きですよね。
元々中国で行われていた追儺という行事が日本風に変わっていったもののようですが、以前お話ししたお正月の風習にも同じように中国から伝わってきたものがありましたね。(門松も平安時代に中国から伝わってきたものが始まりとされています。)
詳しくはないですが、平安時代ってそういう時代だったのですね。
掛け声となる「鬼は外、福は内」という言葉ですが、一部の地域や神社では「鬼も内」という掛け声になっているようです。
鬼を神であると祭っていたり、鬼頭さんや鬼熊さんといった苗字が多い地域では、こういった配慮がなされているとか。
投げる豆には“福豆”という神様のご利益を宿した豆を使います。
大豆を炒ったものを神棚とかにお供えした豆で、まさに魔を滅するに相応しいものですね。
それを自分の歳の数だけ食べることで、神様のご利益を取り込んでいく感じです。
鏡餅も同じような意味合いで食べられていました、やはり物事に意味を持たせるのが好きですよね。
あらゆる物には神様が宿るといった考え方もそうですが、特に日本はこういった意味を持たせるという考え方が根本にある気がします。
スーパーなどでもこの時期になると福豆って売られていますね、鬼のお面とセットになっていたりして。
勿論神棚にお供えした豆ではないとは思いますが、こういうのは気持ちが大切ですからね、野暮なことは言わずにというところで。
子供って全力で投げてくるのできっと痛いですが、全国のお父様方、頑張りましょうね。
他にも邪気を祓う飾りが
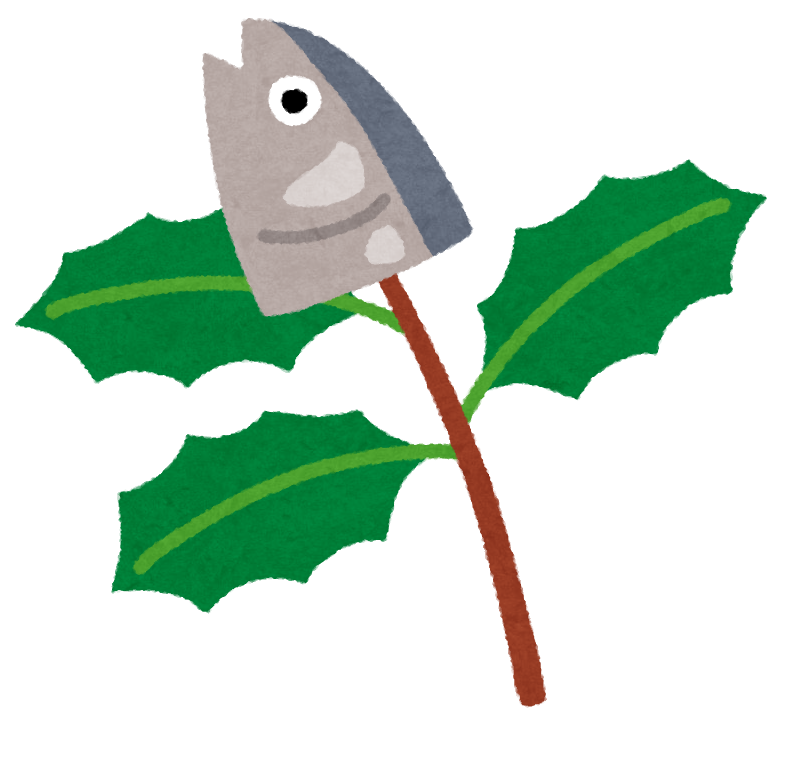
柊鰯(ヒイラギイワシ)という魔除けの飾りがあるそうで、上の画像のように柊の枝の先にイワシの頭を突き刺したものです。
なかなかに面白い見た目ですよね、私は現物を見たことがありません。
イワシを焼いた臭いと煙で鬼を遠ざけ、柊の葉の棘が鬼の目を刺すことから家の中に入ってこられないようにする意味があるそうです。
全国的にも見られる風習とのことですが、やはり臭いの問題や見た目も相まってあまり飾っているところは多くなさそうです。
こうして紹介はしているのですが、私としては正直飾りたくないですね。
臭いと見た目がもうね、家の前に飾ってあったらなんか嫌だなと感じてしまいます。
鳥とかにイワシの頭だけ持って行かれそうですしね。
他にも地域によっては「鬼ぐい」や「鬼おどし」といった名前の魔除け飾りがあるようなのですが、こちらも柊の葉と煮干しであったりといった様子でした。
鬼が嫌がる物を組み合わせて玄関の外に置いておくことで、魔除けとするところは共通していました。
恵方巻は大阪発祥だった?
いつから始まった風習かは不明なのです
恵方巻が現在のようにコンビニなどで見かけるようになったのは2000年代以降、1998年にセブンイレブンが売り始めたことから全国的に広がっていったようです。
ではそもそも恵方巻はいつ頃から食べられていたのかというと、ハッキリとわかる資料はないようです。
1930年頃に大阪の商業組合が広めたという説や、戦国時代の武将が戦の前に太巻きを食べて出陣したら勝つことができたからというもの、といった風に有力な説はあれど確証はないそう。
どれもありそうで何とも言えませんが、個人的には商業組合が広めたという説が現実的にありそうだと思いました、実際に当時配られていた広告も残っているそうです。
出所はともかくとして、実際に人々の間に浸透している以上、既に力を持った風習と言えるでしょう。
恵方巻を食べる時は「節分の日に恵方を向いて、願い事をしながら丸かじりして、言葉を発せずに最後まで食べる」ことで願いが叶うとされています。
恵方は以前もご紹介した”十干”をもとに決められており、2025年は西南西が恵方となっています。
中の具材は”七福神”にちなんで7種類とされているものの、最近ではそういったこだわりはなく、海鮮をふんだんに使ったものや、逆に種類を減らしてシンプルにしているものもあるようです。
こういった行事は信じることが何よりも大事だと思いますので、皆さんも恵方を向いて、心の中でお願いをしてみてはいかがでしょうか。
感想
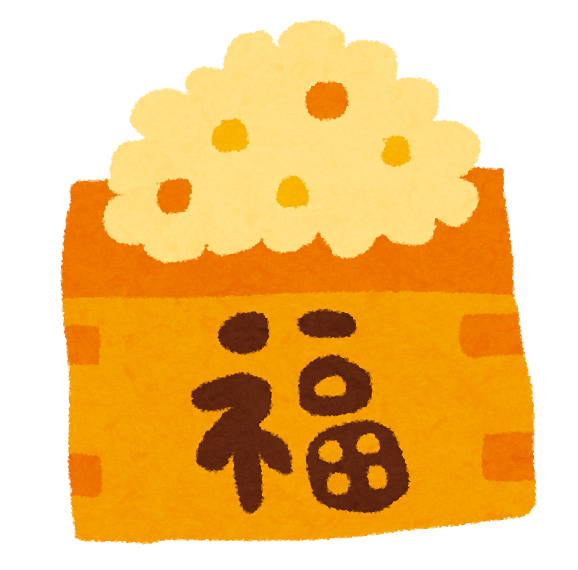
魔を祓い、一年の健康と繁栄を願った節分。
平安時代、遡るなら中国から受け継がれてきた日々を穏やかに暮らしたいと願う気持ちは、今の時代であっても変わらないものだと思います。
信じる気持ちがたくさん集まって、人々の心も救うのが信仰心。
恵方巻を食べながら誰かの平穏を願えば、きっとあなたにも平穏が訪れることになると思います。
それでは今回はこのあたりで。
あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。
Radiotalkで音声配信もしていますので、興味がある方はぜひこちらも聴いてみてくださいね。
番組 #真也のFeelingNight #Radiotalk https://radiotalk.jp/program/155656



コメント