こんにちは、桐生真也です。
私は元々あまり自動車には興味がありませんでした。
子供の頃からトミカでは遊んでいましたが、車の名前やブランドなどには興味が向かなかったのです。
ですがとある海外ドラマを見ていた時に、上の写真の車に一目惚れ。
シボレー・カマロ。
重厚なボディにパワフルな走り、何よりも顔つきがカッコいい。
それ以来、車を選べるようなゲームでは必ずカマロがないかを調べ、必ず乗っているくらい大好きになりました。
残念ながらもう新車は製造していないらしく、中古でも800万円以上したりもするので一生乗れないとは思いますが、時折走っているのを見かけると一人で興奮してしまいます。
カマロが好きになって以来、車の名前やブランドにも興味を持ち始め、映画ワイルドスピードに大興奮するようになりました。
さて、そんな現代では当たり前のようにある自動車。
歴史の授業などでも初の有人飛行を成功させたとしてライト兄弟は有名ですが、初の自動車については言及されているのを見たことがありません。
正直飛行機よりも自動車の方が身近ですし、取り上げないのは不思議です。
気になる!
そもそも自動車っていつから存在するのでしょうか?
どういった歴史を経て現代の自動車に変わっていったのでしょう。
普段から利用している自動車ですから、気になってしまいました。
浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。
気ままにお付き合いいただけたら幸いです。
車の歴史
大砲と蒸気機関

世界で初めて自動車が作られたのは、1769年のフランス。
当時のフランス陸軍大臣のエティエンヌ・フランソワ・ド・ショワズールは、当時の最新技術であった蒸気機関を用いた大砲運搬用の乗り物の作成を命じ、軍事技術者であったニコラ=ジョセフ・キュニョーにて開発された。
前輪1・後輪2の前輪駆動三輪車であり、蒸気機関により駆動し、運転手による操作もできた。
1769年に設計の半分の大きさで試作1号機が制作され、翌70年には設計図通りの試作2号機が制作された
全長7.32m、走行速度は四人乗りで時速9km程度であったがスピード制御のブレーキはなく(今でいうところのサイドブレーキはついていた)、蒸気機関の設計が甘く12~15分しか動かない上に途中で水を補給できない構造で、再稼働には15分程度休ませなければならないといった問題を多く抱えるものであった。
この試作車は当時「火の機械」と呼ばれ、後に「キュニョーの砲車」と呼ばれるものになる。
そして公開試運転時にハンドル操作で制御できず接触・破損し、これが世界初の交通事故となる。
なお、試作2号機は現在もパリ工芸博物館に現存し、実際に見学することができる。
やっぱりこういうのは調べていくと面白いですね。
世界初の自動車で世界初の交通事故、あらゆる意味で歴史的瞬間ですね。
残念なことにこの蒸気自動車は本来の役目を果たすことなくプロジェクトが中止、以降19世紀にドイツのカール・ベンツ(メルセデスベンツの創始者)がガソリンエンジンを発明するまで、自動車の技術は停滞しているようです。
技術的な問題も、かなり重大な問題です。
制動用のブレーキが付いていなかったということは、走り出したら停まらないということですから、水が無くなるかぶつかるしか停止する手段がないということ。
試運転は当然舗装された平地で行ったのでしょうが、戦争中に運用されるのであれば、舗装された平地なんてほとんどないでしょう。
ハンドル操作にしても車体が重すぎて相当な腕力が必要だったようですし、時速9kmとなっていますが、実際には補給と蒸気機関の休憩を含めると1時間に3.5~4km程度しか移動できないようですね。
当時の運搬は馬車が主流であり、馬の走破性の高さも鑑みると、この時点ではまだまだ勝ち目はなかったでしょう。
ちなみに扱いとしては世界初のトラックとなるそうです、大砲運搬用の自動車なので。
しかしながら、まだ運用され始めたばかりの蒸気機関を個人で操作可能な大きさまで小さくし、事故になってしまったとはいえ実際に駆動させたことは称賛されるべき発明だと思います。
フランスという先進国の後ろ盾があったからこそ研究できたとはいえ、資金の問題や技術的な問題に悩まされながら、実際に完成させてみせたことは凄まじい努力の賜物ですね。
自動車という分野においてこれほど大きな功績を打ち立てているのですから、学校の授業で登場しても不思議はないと思うのですが。
激動の19世紀と拡大の20世紀

19世紀頃になると世界中で自動車の発明が活発に行われました。
先程も出てきたドイツのカール・ベンツによるガソリンエンジン自動車、同じくドイツのルドルフ・ディーゼルが開発したディーゼルエンジンが登場しました。
蒸気自動車も進化しており、1827年頃にはイギリスで蒸気機関の都市バスが運行されており、10名ほど乗車できたそうです。
そして既にこの頃には電気自動車も登場しており、世界で初めて時速100kmの壁を超えたのは電気自動車だったようで、1899年にベルギーのカミーユ・ジェナッツィがジャメ・コンタン号で時速105.92kmを記録しています。
蒸気・ガソリン・電気の三つ巴となった激動の時代。
この中で時代を制したのは、皆さんもお馴染みのガソリンエンジン自動車。
きっかけは20世紀初頭の1908年。
アメリカのフォード社が発売した「モデルT」という車の登場でした。

それまで自動車は富裕層だけが持つことができる高価な物であり、一般にはそれほど普及していませんでした。
そんな中でフォード社は工場でのベルトコンベア式組み立てや、部品の互換性などで安価で大量に自動車を生産できる体制を整え、自動車の一般普及に大きく貢献しました。
それまでのアメリカでは電気自動車が主流と言える状況でしたが、電気自動車の航続距離の短さが改善できず、またアメリカで油田が発見されたことによりガソリンの安定供給が始まったこともガソリン自動車の普及を後押ししたようです。
かのトーマス・エジソンもバッテリーの研究はしていたようなのですが、航続距離の解決には至らなかったのでしょう。
この頃には現代で言うところのレンタカーサービスも始まっており、自動車業界が大きく発展した時代と言えますね。
自動車レースも盛んに行われており、現代でも残っているプジョーにシボレー、フォードやルノーといったブランドが活躍したそうです。




どのブランドも日本で走っているのを見かけるくらい有名なブランドですね、まさに錚々たるメンバーです。
なんとなくプジョーとルノーが多く走っているイメージがありますね、特にルノーは日本のコンパクトカーくらいの大きさなので走りやすいからでしょう。
車自体のデザインも変わってきていて、当初は箱型の角ばったものが多く、馬車の延長といったデザインが多かったようです。
その後はいわゆるスポーツカーという種別が現れ始め、早さを追求するために流線型の形の車が増えていったみたいですね。
現代のスポーツカーはもうぺったんこで尖ってる形がほとんどですね、風の力で車体を地面に押し付けるのに最適な形なのでしょう。
しかし大きく普及した影響として大気汚染が深刻化し、これから先も改善に取り組むべき環境問題となってしまっています。
もちろん原因は自動車だけに限らないですが、原因の大きな要因であることは否めないでしょう。
これから先、自動車をどのように変化させていくかが、地球環境に大きく影響することは間違いありません。
新しい自動車のかたちとこれから
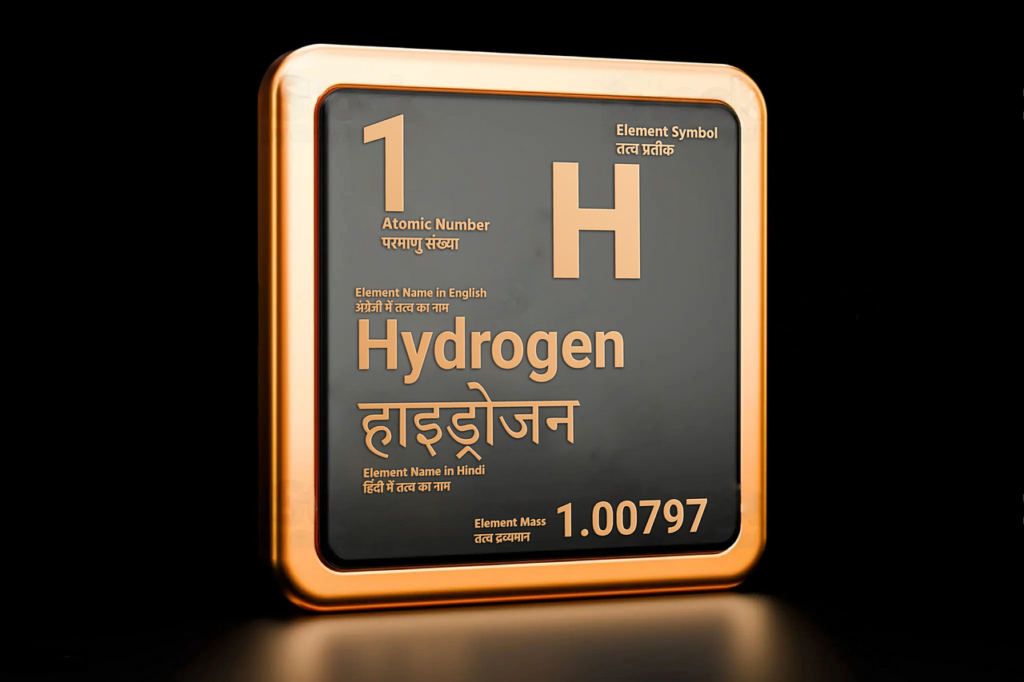
近年になって地球温暖化を含む環境問題が深刻化し、遠くない未来に地球環境は大きく変わってしまうだろうとされています。
化石燃料の枯渇に伴う問題もあり、ガソリンに依存する自動車はいずれ使えなくなってしまいます。
そのため、世界的に各自動車メーカーは電気自動車へ開発をシフトしていく流れになっており、多くの自動車メーカーが既にその先発となる自動車を発表しています。
充電するための施設も徐々にガソリンスタンドを中心として拡大されつつあり、やがて充電スタンドのような専用施設も現れてくると思います。
また、ガソリンに変わる代替燃料として水素が注目されていますね。
水素は燃焼しても温室効果ガスが発生せず、精製するための資源にも困らず再生利用も可能であることから、これから先は電気と水素を利用した自動車に変わっていくと思われます。
実際に水素エンジンを搭載したバスも見かけるようになりましたし、もっと研究開発が進めば、一般にも利用可能なほど普及していくでしょう。
水素は電気自動車と比べても補充がしやすく、燃焼効率も高い物質ですから、自動車との親和性は高そうです。
自動車のエンジンのみならず、ゆくゆくは水素を利用した発電施設や調理器具なんかも出てきそうですね。
水の惑星地球ですから、水素は豊富にありますし。
だからといって際限なく使っていては別の環境問題に発展しそうですから、どうか同じ轍は踏まないよう発展していってほしいものです。
他にも車体の軽量化による燃費の向上、ハイブリッド車の増加など、素人目には徐々に状況は良くなってきているように感じます。
科学の発展は戦争の歴史と言われたりもしますが、何事も使う人次第。
どうか科学者たちには頑張ってもらいつつ、我々も日々の生活の中で、環境を意識した行動を少しでも続けていかなければいけないと感じます。
人間目線ではありますし、たったの数千年で地球環境を破壊し続けた結果なので、地球に意思があれば今更何だと憤慨されそうですが。
それでは今回はこのあたりで。
あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。



コメント