こんにちは、桐生真也です。
今日で2024年も終わります。
毎年この時期になると、一年があっという間だったように感じてしまいます。
楽しかったこと、苦しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと。
色々な想い出や出来事を思い返しながら過ごすこの時間こそが、年を越すための最後の準備なのかもしれません。
皆さんの2025年が、穏やかに迎えられることを願っております。
さて、この頃あちこちで見かけるようになったのが門松。
通例では12月26日から門松を置きますね。
竹と松で作られたのどっしりとしたその佇まいは、まさにお正月といった風情を感じさせます。
そんな門松の話題になった時に、職場の方がこんなことを言っていました。
門松って二種類あって、武田と徳川が関係してるんだよ。
二種類?見た目の華やかさとかではなく、種類?
気になる!
武田と徳川って、戦国時代の?
戦国時代の一大勢力だった両者と門松に何の関係があるのでしょう。
戦国時代も好きなこともあって、気になってしまいました。
浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。
気ままにお付き合いいただけたら幸いです。
門松の起源とは
そもそも門松というものはいつからあるのでしょうか。
古くは、木の梢に神が宿ると考えられていたことから、門松は年神様を家に迎え入れるための依り代としての意味合いを持ちます。「松は千歳を契り、竹は万歳を契る」と言われており、古代中国でも松は「祀る」に繋がることから、生命力や不老長寿の象徴とされてきた。
松を門に飾る風習は平安時代には中国から伝わってきたとされており、以降の文献には度々門松に関する記載が見られるようになる。
以前クリスマスのもみの木のお話しをしたときにも、生命力の象徴とされていました。
トドマツという植物は名前に松を持っていますが、こちらはモミ属とのことなので、松ともみの木は近しい種類の植物なのかもしれません。
一年中緑を茂らせ、比較的過酷な環境下でも成長することからも、生命力の象徴とされるのも納得です。
門松に限らず、盆栽や庭園づくりでも松は現れますし、古くから日本では大切にされてきた植物なんですね。
ちなみに中国から伝わってきたのを起源とする門松ですが、中国では正月に飾るのは松よりも桃が多いらしく、桃の木を飾る風習が伝わってきた頃には既に門松の文化が根付いていたことから、日本では定着しなかったようです。
元は中国の文化であっても、日本らしく変化して定着していったのですね、。
また、竹を斜めに切る時に節の部分で切ることで、切り口が笑顔のように見えることがあります。
これは笑い竹の門松と呼ばれ、笑う門には福来るということわざにちなみ縁起が良いとされているそうです。
私が普段通勤で使う駅にも門松が飾られていましたが、確かに少し笑っているように見える切り口でした。
人々が笑い、幸福が巡っていく。
ことわざのように、来年も笑顔が溢れる駅になってくれるといいですね。
武田と徳川

門松は読んで字の通り松が主役なのですが、鎌倉時代以降は一緒に竹も飾るようになりました。
竹も長寿の象徴であるという考え方から、一緒に飾るようになったようです。
そんな門松ですが、鋭く斜めに切られた竹の方が主役とするイメージの方が多いのではないでしょうか。
私も竹をイメージしてしまいます、松の部分は華やかさを出すためのものとばかり思っていたくらいです。
斜めに切られた立派な竹の周りに松や飾りが添えられているイメージですし、私の見かける門松もみんなこのような形でした。
ですが、どうやらこの竹の切り方に種類があるようなのです。
門松の竹の先端の形状は、斜めに切ったもの「そぎ」、真横に切ったもの「寸胴」の二種類がある。元々は「寸胴」しかなかったが、一説では徳川家康が三方ヶ原の戦いで武田信玄に敗れた後、武田方から送られた「松枯れて 竹類いなき 明日かな」(松平の出自である徳川家康が滅び、武田が類い無く栄える)という句を、「まつかれで たけだくびなき あしたかな」(松平氏は滅びず、武田の首が落ちる)と読み替えて、竹を斜めに切り落とした門松とともに送りつけたと伝承されている。
門松を武田信玄の本国であった山梨県では、「寸胴」の門松を「武田流門松」と称し、県庁舎に飾っている。武田流門松では、土台のしめ縄が武田の家紋の「武田菱」に編まれているそうです。
斜めに切り落とした理由が思っていたより物騒でした。
とはいえ時は戦国時代。
武田勢からの容赦のない煽り文句に対し、その文句を読み替えて切り返すあたり徳川勢がまだまだ負けていないという様子がうかがえます。
実際に何度か窮地に立たされながらも長きに渡る天下統一を果たしているのですから、徳川恐るべしです。
そして流石は山梨県、きちんと「武田流門松」を飾っているのですね。
家紋までしめ縄で表現しているあたり、強い地元愛を感じます。
私は「武田流門松」というものを見たことがありません、門松を作成している企業さんでも「そぎ」のものしか扱ってなさそうでした。
また飾り方には東西で違いがあるようで、関東は土台を藁で縛り、関西は竹で縛っているそうです。
飾り方も、関東はシンプルなものが多く、関西は豪華な飾りが多いようです。
今回使わせてもらっているイラストの門松は藁に見えますが、関東のものなのでしょうか。
また、「そぎ」の門松が全国的に普及したのは、笑い竹の門松の縁起の良さが理由みたいですね。
企業さんが「そぎ」で作成するのも納得です。
徳川が天下を取ったから「そぎ」が多いのかとも思っていたのですが、もっと人々の幸福を願ったが故の理由でした。
縁起物にはやはり、人々の優しい気持ちが受け継がれているのですね。
感想
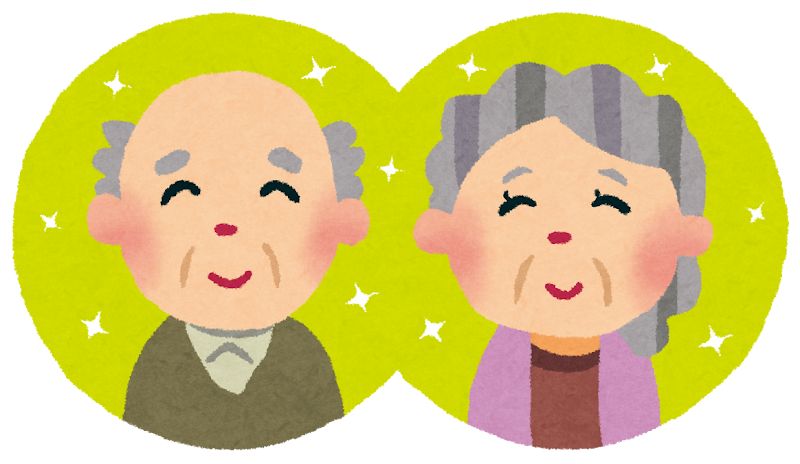
ちょっと説明が長くなってしまいました。
竹の切り口にも幸福を願う思いがあり、家族の幸せを想う気持ちが表れているのですね。
2024年も間もなく終わります。
新たな年になる前に、ほんの少しでも、どうか大切な人を思い浮かべてみてください。
今は目の前にいないかもしれません、それでも思いは伝わります。
どうか新しい年が、皆さんと、皆さんの大切な人にとって実り豊かな一年になりますように。
三が日は、私も少しゆっくりさせていただきますね。
それでは今年はこのあたりで。
あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。
Radiotalkで音声配信もしていますので、興味がある方はぜひこちらも聴いてみてくださいね。
番組 #真也のFeelingNight #Radiotalk https://radiotalk.jp/program/155656



コメント