こんにちは、桐生真也です。
4月になって、新しい環境で頑張っている皆さんお疲れ様です。
新たに学ぶべきことが多く大変だと思います、ですが基本はこれから先のすべてに関わる大事な部分ですから、どうかめげずにしっかりと学んでください。
そして新人さん達に色々と教えなければならない立場の皆さん、気苦労をお察しします。
ハラスメントなどに気を遣いながら教えるのは大変ですよね、どこまで言っていいものか言葉を選ぶ日々だと思います。
物覚えにも個人差がありますから、中々言ったことを覚えられない人もいることかと。
ですがどうか比べたりせず、それぞれに合ったペースで教えてあげてください。
今回はそんな研修や指導時に使える大事なことやコツをお伝えしていきたいと思います。
少しでも今後のご指導の役に立てるなら幸いです。
拙い文章ですがご容赦ください。
気ままにお付き合いいただけたら幸いです。
緊張をほぐし相手にとっての居場所になってあげましょう

人となりがわからない相手とコミュニケーションを取ることは、大なり小なりストレスに感じるものです。
どういった距離感で話せばいいのか、どういう性格の人なのか、そういった部分が不透明なままでは緊張してしまい、会話が頭に入らないなんてことも。
こんな状態ではせっかく丁寧に説明しても結果に繋がらず、お互いに面白くない気持ちになってしまいます。
私も新人時代に経験がありますが、そもそも教えてくれていた人の名前すら思い出せないこともありました。
名前も名札を見て覚えろと言わんばかりに名乗られることもなく、いきなり業務のやり方の説明が始まり、緊張状態のままペースが乱れてしまったためです。
まずは自分のことを知ってもらい、話しやすい相手なのだということを相手に感じてもらいましょう。
下に私が実践している会話の内容や接し方を書いておきますので、参考にしてみてください。
話しやすい相手だと感じてもらえれば自然と緊張は解けていき、余計な力みがなくなります。
そうなってくれればその人のポテンシャルは充分に発揮できますし、教えている内容にも集中できるようになるでしょう。
自分の過去を振り返ってみて、気楽に接することができる相手とのことの方が覚えているなんてことありませんか?
嫌な先輩や先生のことは、嫌な記憶としてしか残らないものですから。
そして何よりも、新しい環境に来て、自分は何処に居れば良いのか判らない、そんな不安の解消にも繋がります。
酸いも甘いも共有できる仲間、不安や苦痛を相談できる先輩、この人と一緒にいると気楽でいられる、そういった感情を持ってもらえたら最高ですね。
相手の年齢に合わせて会話の内容を変えられたら素晴らしいです、各年代別に広く浅く知識があると便利だと思いますよ。
お互いに友人のように親しく、しかし敬意を忘れない、こんな関係性が理想ですね。
研修しなくちゃと気負いすぎないで、お互いの緊張をほぐすためにも、関係性の構築に時間をかけてみてはいかがでしょうか。
丸暗記ではなく理由も添えて

私の話ではあるのですが、丸暗記するのがとても苦手です。
思い出すとっかかりが無いので、すぐに思い出せないのです。
ですが、何故そういったことをするのか、何故このような結果になるのかという理由や道筋まで教えてもらえると、すごく納得できて覚えていられるのです。
ただ誰かに言われたことよりも、自分の中で納得できたことは印象に残りやすく、覚えていられます。
情報を”点”で覚えるのではなく、複数の情報を流れとしての”線”で繋ぎ、複数のカテゴリーをまとめて”円”にして覚える。
教える相手がそうやって情報を自分の中で整理できるように、情報同士を繋げて覚えていられるように教える順番を考えるのが大切です。
”これはこうする”だけではなく、”これはこういう理由で””こうする”といったように、二つの情報を繋げて伝えるようにしてみてください。
教えている相手の”何故”に応えることも大切です、理由や過去の出来事も交えればより印象深くなりますよ。
とりあえず覚えてと言われた時の胡散臭さと言ったら、あぁこの人に教わるのは嫌だなと思わせるに十分なレベルです。
信頼関係や尊敬の念が一気に消し飛びかねませんので、もしわからないのであれば素直に自分も知らないから調べてみるねと、応えられないことに対する非を詫びることも大切ですよ。
もちろん丸暗記でなければならないようなこともあるでしょう、特に固有名詞だとか略称は丸暗記で覚えるしかないですから。
マニュアルがあればそれが一番ですが、持ち歩けるサイズではないでしょうし、紛失の恐れもありますから持出し禁止となっていたりもしますよね。
自然と現場では口頭で伝えてメモをさせるといった方法になってしまいます。
ただできれば相手にメモさせるのではなく、事前に一覧にして渡しておくといいでしょう。
書かせて覚えさせるというのも解らなくはないのですが、大抵が立ちながらメモさせたり、話すペースが早くて書くのが追いつかなかったりしているのを見かけます。
それだとメモに抜けがあったり、殴り書き過ぎて読み返せなかったり、そもそもメモすることに意識が向きすぎて内容を理解していなかったり。
せっかく教えたのに時間が無駄になってしまいますし、自分でメモした情報は不確かな情報となってしまい、見直しても不安が抜けないこともあります。
しかし先輩が用意してくれた情報であれば、自分がメモしたものよりは信用のおける情報と思えませんか?
何度でも見直せますし、殴り書きでもないから読みやすく、もしPCで作ったものであれば他の人にも何度だって渡せます。
覚えやすい順番や覚えるべき順番で用意することができるので、現場で思いついた順に教えるよりも効率がいいです。
メモさせる時間も勿体ないですし、浮いた時間を現場だからこそ教えられる実技に当てるべきです。
多くの場合研修って日数とか時間が限られていますから、事前準備をしっかりすることで効率よく効果的な研修をすることができますね。
マニュアルなんて用意されていないことも多いみたいですから、独自に用意したマニュアルというのは便利ですよ。
マニュアル作りの時間が取れなくて困っているということも多いでしょうけれど、ちょっとだけ頑張って作ってみてください、便利さが実感できるはずですから。
”何故?”と思うことを癖にさせる
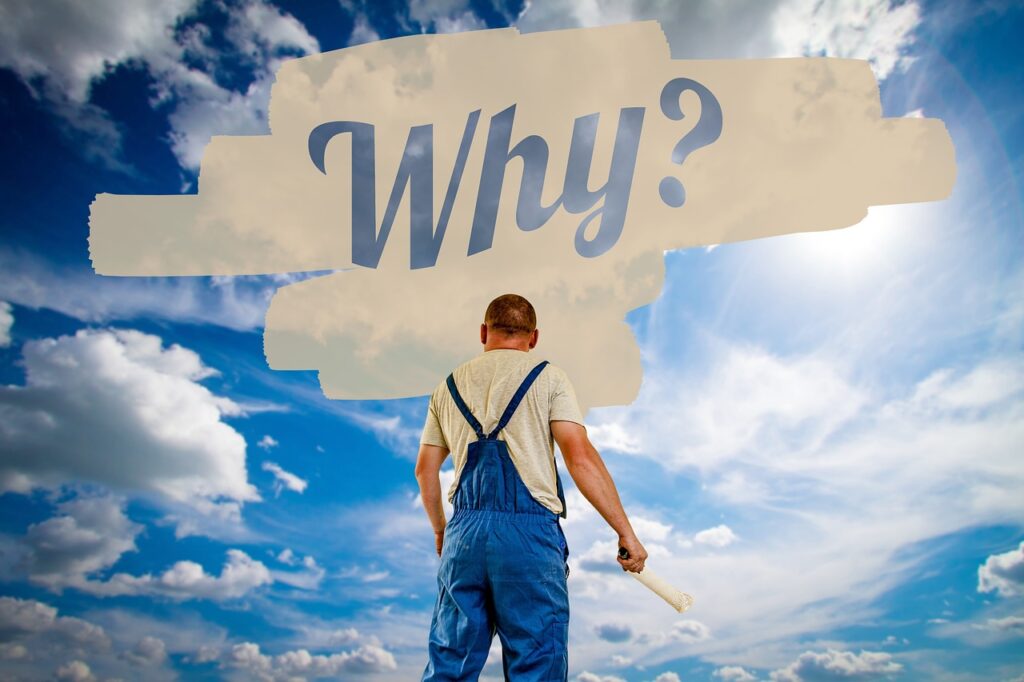
このブログのテーマの一つでもありますが、疑問や気になるという気持ちは、知識を吸収する上で非常に大きな要素だと思っています。
興味のあることは覚えやすいですし、疑問に感じた時点でその事柄に意識を向けているということですから。
ぼんやりと多くの知識を眺めるよりも、一つに集中できている状態なのです。
そういった状態になる回数を意識的に増やす、そのために疑問を感じることを忘れないようにと伝えるようにしています。
何故こういうことをしているのだろう、何故こんな行動をしたのだろう。
業務などに対する疑問、誰かの行動に対する疑問。
そういった疑問を抱かせ、その疑問の答えを思考させることがとてもいい訓練になります。
言われたことだけをやるのではなく、感じた疑問や目の前にある問題に対して自ら考えて行動できるようになるための訓練です。
思考を止めないこと、間違っててもいいから自分の考えを思い浮かべてみること。
指導する際に最初にそう伝えて、理由を説明する前にどうしてこういうことをするのか考えてみてと促すことで、相手がどんな風に考えを巡らせるのか、その一端を見ることもできます。
物事を深く考えるタイプなのか、頭の回転が早いのか、興味ややる気がないのか。
答えてくれた内容があまりにも見当違いであるなら修正し、僅かに違う程度ならその考え方も認めた上で整えてあげる。
また、もし誰かにわからないことを聞く時があるなら、自分の考えも添えて質問するようにしなさいとも伝えています。
自分はこう考えていますが合っていますか?という風に質問すると、教える側も感心してくれるよと。
実際、考える癖をつけている人は覚えもよく、伸びも良くなります。
しかしながら誤った考えのままで思考を繰り返しても悪影響ですから、時々様子見のように質問してみて、修正をしてあげる必要はありますが。
若い感性で思わぬ改善案を思いついてくれたり、新しい商材のアイデアのキッカケとなることもあるでしょうから、若い人の可能性を広げる上でも考えさせることは大切です。
最近はネット社会となり、調べれば答えがすぐに見つかる時代。
ですが見つかるのはあくまでも既に起こった出来事の解決方法や、単純な知識でしかありません。
まさに今目の前で起こっていることへの対処というのは、そういった知識を持った上で考える必要があります。
だからこそ、いつだって自分で考えることができるということは力になります、そのお手伝いをしてあげてください。
思考を自然と巡らせること、これが簡単なことでもなくて、意識していないと難しいことなのです。
慣れたことほど疑問は抱かなくなる、見慣れているものを見ている時は思考が停止している。
思い返してみるとそうだなと思うこともあるかと思います、常に考えるってとっても大変ですし。
でもそれがある程度できるようになれば、動じなくなったり、いつも冷静でいられるようになります。
自分でそれを意識してできるようになれるか、その一歩目を促してあげてくださいね。
さいごに
長くなってしまいましたが、一つでもこの記事を読んでいる人の役に立てたら幸いです。
学生の頃から人に研修する立場であることが多かったので、実際にやってみて感じたことなども多く盛り込んだつもりです。
とはいえ、これが正解というわけではありません。
人の数だけ方法は違うし、同じことをしても結果はそれぞれ違います。
個人の能力もあるとは思いますが、教える人と教わる人、お互いの意識が合致した時に最高の効果が表れるのだと思います。
教える側に立つ皆さん、教わっている側の皆さんも。
相手のことをよく見るという点に関しては共通していますから、どうかしっかりと向き合ってあげてくださいね。
それでは今回はこのあたりで。
あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。



コメント