こんにちは、桐生真也です。
今日からお仕事が始まったという方、お疲れ様でした。
休みが明けるのは嫌なものです、子供の頃のように夏休みや冬休みがもっと長ければと考えたことがある人はきっと多いはず。
私もはまっているゲームがある時期なんかは、ずっとやっていたいと思ってしまいます。
お仕事やそれ以外の事でも、いきなり頑張りすぎないでくださいね。
ゆっくり、徐々にペースを上げていけばいいのです。
車のギアを上げていくようなものです、初めからトップスピードを目指したってできませんから。
さて今回は前回の続きで、十二支のお話です。
それぞれの意味を含めてお伝えしていきたいと思います。
前回の記事をご覧になっていない方は、是非読んでみてくださいね。
ちなみに今回のサムネイルに使われている画像は韓国の十二支を示したものですが、イノシシがブタになっていますね、ちょっと見づらいですが右上の方です。
浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。
気ままにお付き合いいただけたら幸いです。
十二支に込められた意味とは
それでは順番にお話していきますね。
自分の干支にはどんな意味が込められているのか、是非知っていってください。
ネズミ(子年)
”子”は新しい生命が種子の中に萌し始める状態を指します。ネズミは繁殖力が高いことから、子孫繁栄・臨機応変の意味を込められています。
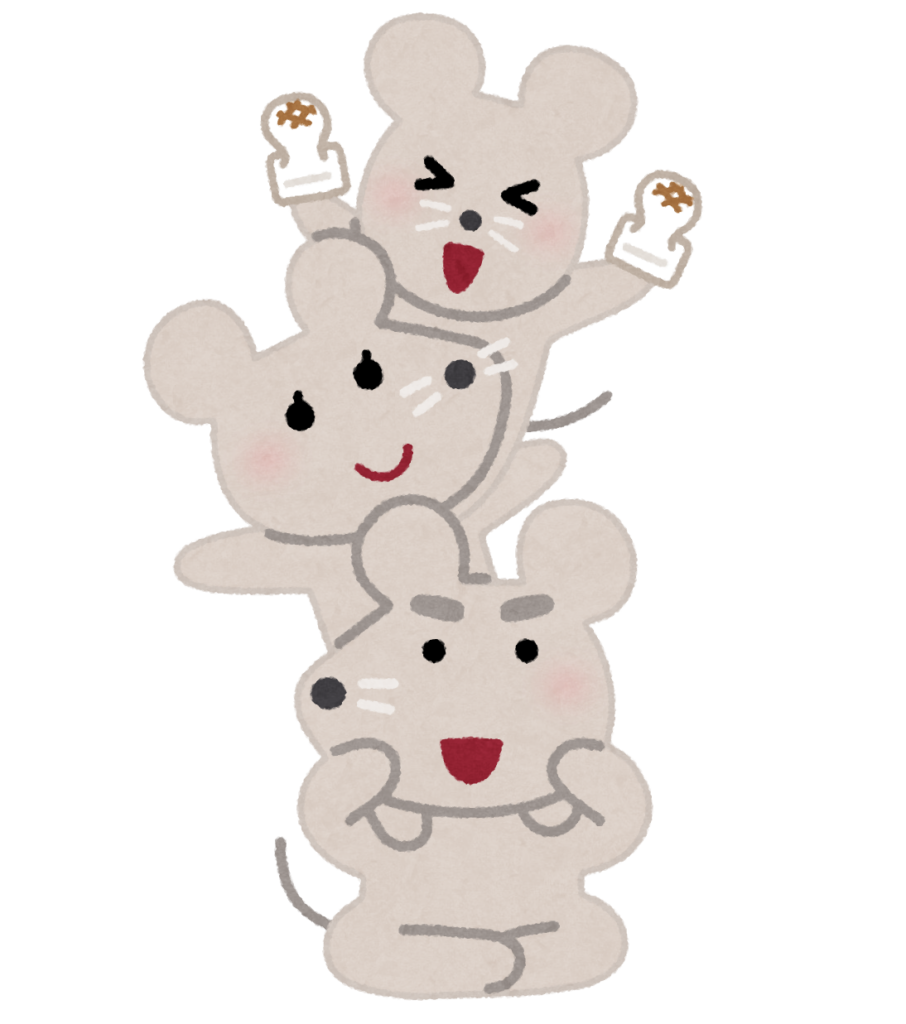
ウシ(丑年)

”丑”は芽が種子の中に生じてまだ伸びることができない状態を指します。ウシは力強く、昔の人々の生活を助ける欠かせない動物でした。そこから忍耐力・誠実さの意味を込められています。
トラ(寅年)
”寅”は春が来て草木が生ずる状態を指します。トラはその勇猛果敢さから、決断力・才覚の意味を込められています。

ウサギ(卯年)

”卯”は草木が地面を蔽うようになったことを指します。ウサギは穏やかで平和、また高い跳躍力を持つことから、温和・飛躍の意味を込められています。
リュウ(辰年)
”辰”は草木の形が整った状態を指します。リュウは古代より中国で権力の象徴であり、権力・大事を成すの意味を込められています。

ヘビ(巳年)
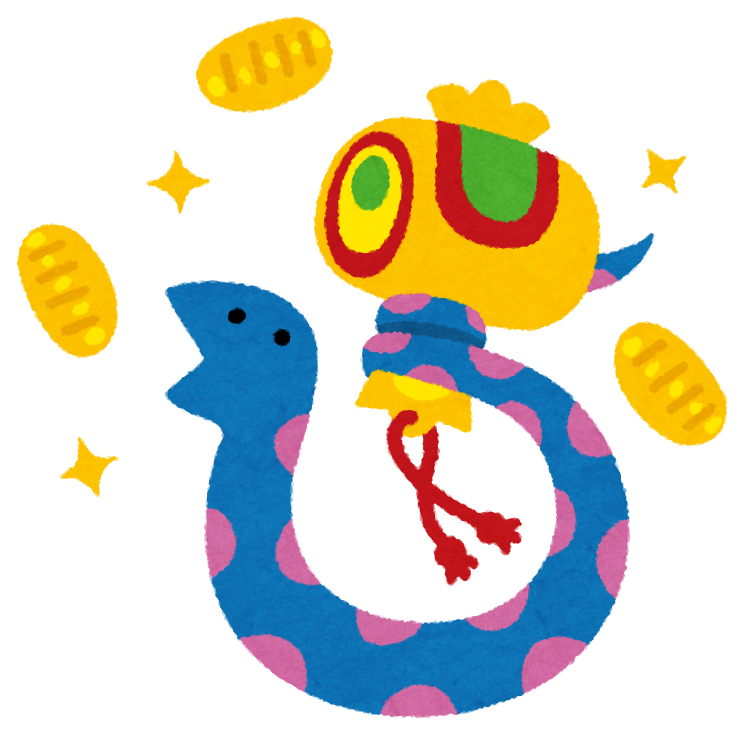
”巳”は草木の成長が極限に達した状態を指します。ヘビは脱皮を繰り返し大きくなることから、生命力の象徴とされてきました。永遠・再生の意味を込められています。
ウマ(午年)
”午”は草木の成長が極限を過ぎ、衰えの兆しを見せ始めた状態を指します。ウマも昔の人々の生活を支え、人を乗せることもあることから、豊作・心が広いの意味を込められています。
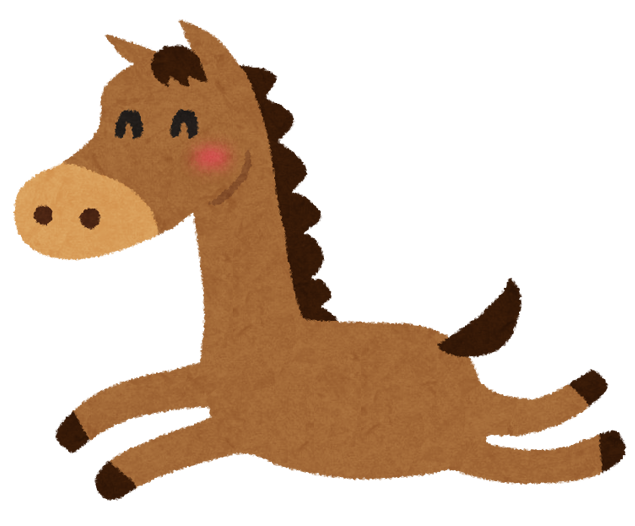
ヒツジ(未年)

”未”は植物が鬱蒼と茂って暗く覆う状態を指します。ヒツジは穏やかで集団生活をすることから、家内安全・協調性の意味を込められています。
サル(申年)
”申”は果実が成熟して固まって行く状態を指します。サルは賢く、神の使いとも信じられていました。そのことから賢者・好奇心の意味を込められています。

トリ(酉年)
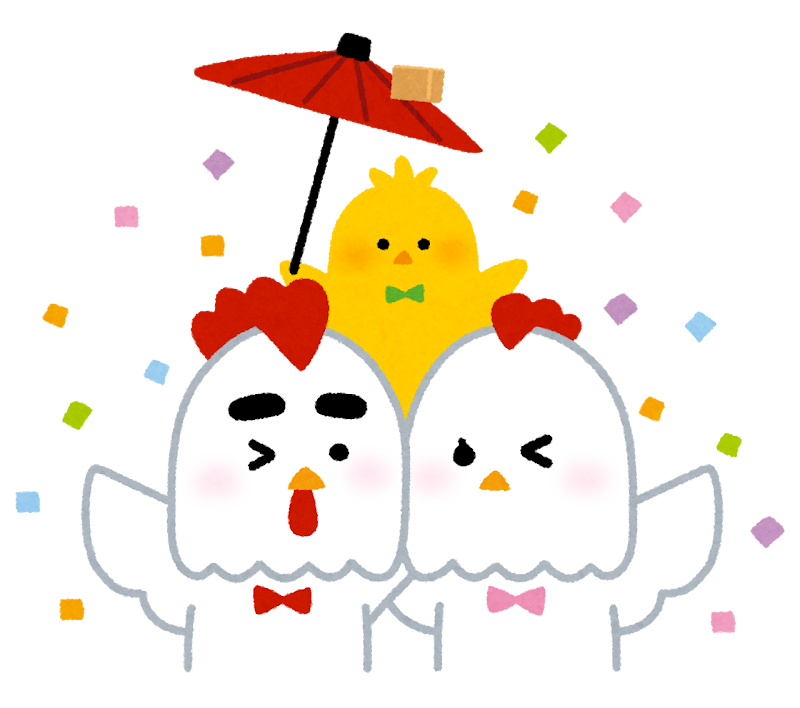
”酉”果実が成熟の極限に達した状態を指します。トリとはニワトリのことであり、酉の市という商売繁盛を願う祭りもあることから、商売繁盛・努力家の意味が込められています。
イヌ(戌年)
”戌”は草木が枯れる状態を指します。イヌは忠誠心が強く、古くから人間と生活を共にしてきたことから、忠誠心・真面目の意味が込められています。

イノシシ(亥年)

”亥”は草木の生命力が種の中に閉じ込められた状態を指します。イノシシの肉は万病に効くとされていたり、猪突猛進という言葉もあることから、無病息災・一途の意味が込められています。
ちょっと多くて読むのが大変かと思いますが、いかがでしたか?
自分の干支がどういった意味を持つのか、私も初めて知りました。
私は午年なのですが、心が広いかと聞かれても首を傾げてしまいそうです。
こういう言葉に意味を持たせた昔の人たちって、とてもポジティブだったのだなと思ってしまいました。
こういうポジティブな考え方で自分を高めていく、素敵な考え方だと思います。
言葉に込められた意味を知ることで、その一年の指標となれば素敵ですね。
十干と還暦
話はちょっとだけ横道に逸れますが、十二支と合わせて”十干”という言葉があります。
最初に”甲”、次に”乙”と続きます。
”甲乙つけがたい”という慣用句でも使われているように、1から10まであり、以下のような順番で示されます。
- 甲(コウ・きのえ)
- 乙(オツ・きのと)
- 丙(ヘイ・ひのえ)
- 丁(テイ・ひのと)
- 戊(ボ・つちのえ)
- 己(キ・つちのと)
- 庚(コウ・かのえ)
- 辛(シン・かのと)
- 壬(ジン・みずのえ)
- 癸(キ・みずのと)
実は干支とはこの”十干”と”十二支”を合わせたものであり、全部の組み合わせで60組あります。
2025年は乙(きのと)の巳(み)年なので、乙巳(きのとみ)の年となります。
いわゆる干支とはこの”きのとみ”などの十干十二支を指すのですが、日本では十二支を指して干支と呼ばれるようになりました。
年賀状などで十二支を描くことが多いことから、こちらだけが残って定着したようです。
十干と十二支は年が明けるごとに進むので、乙の次は丙、巳の次は午なので、来年は丙午(ひのえうま)の年となります。
この十干十二支が一回りするのが60年、それを還暦と呼びます。
還暦という言葉だけは今も多く使われていますよね、区切りがいいからでしょうか。
最近は定年の年齢も延びましたが、同じく60歳というところからも、区切りとして使いやすい言葉だったのかもしれません。
生まれた年が何の干支だったのか知りたい場合は次の計算式で出ます。
(生まれ年 − 4) ÷ 60 → 余りの数字に+1
2025年で計算すると、余りは41になるので1足して42。
十干は一の位を見ればいいので、二番目の乙。
十二支は更に12で割った余り、6となるので、六番目の巳となりますね。
是非自分の干支を調べてみてくださいね。
感想

十干十二支、初耳でした。
今回はあまりにも組み合わせが多く書ききれないので載せませんでしたが、それぞれの組み合わせにも運勢などの意味がありますので、興味があったら調べてみてください。
こういうことを調べていると、身の回りには知らないことがたくさんあるのだと実感しますね。
どうかこのブログが、あなたの知らなかったを埋められることを願って、今年も頑張っていきますね。
それでは今回はこのあたりで。
あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。
Radiotalkで音声配信もしていますので、興味がある方はぜひこちらも聴いてみてくださいね。
番組 #真也のFeelingNight #Radiotalk https://radiotalk.jp/program/155656



コメント