こんにちは、桐生真也です。
少しずつ花粉も落ち着いてきて、車にくっつく黄色も減ってきたように感じます。
花粉症の皆様におかれましては、日々の生活が少しでも楽な季節に早くなってほしいと願うばかりでしょう。
私は子供も新学期が始まりまして、なんとか学校に行ってくれていて安心しております。
さて前置きはこれくらいにして、タイトルの通りちょっとした疑問が溜まってまいりました。
気になる!けど内容的に一行で終わっちゃう!
そんな感じの疑問がまた溜まってきたので、またもやそんな感じの内容を細々とお伝えしていこうかと思います。
ほとんど個人的な備忘録ではありますが、もし丁度気になっていたことがあれば幸いです。
浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。
気ままにお付き合いいただけたら幸いです。
ちょっとだけ気になった事柄たち
国庫金って言うけどどこに保管されているの?

日本の国家資産、いわゆる国庫金は日本銀行本店にのみ集約されて管理されている。現金だけではなく、有価証券や不動産なども含めて管理されている。
日本銀行を銘打たれているだけあって、やはりこういった金銭の管理も任されているのですね。
ちなみに国の借金、いわゆる国債は1317兆円にも上るそうです。
もっと言うとアメリカの国債は36兆2000億ドル、1$150円くらいとすると5503兆8480億円くらいだそうで、なんだかもうよくわからないですね。
アメリカと比べれば安いだろうけれど、そもそも国土の広さとか色々と考えると、日本の狭さでこの金額は異常なのでは?
残念ながらこういう話はちっとも解らないので調べただけではありますが、興味が出てきた方はもう少し突っ込んで調べてみてもいいかもしれませんね。
私はもちろんここでお終いにしますよ、すごい勉強しなくちゃ理解できそうにないですし。
香川県にはうどんのグルテンを大量に含んだ水の処理施設がある?

その名も”高濃度うどん排水処理施設”。
冗談みたいな話ですがどうやら本当らしく、うどんを茹でた水にはデンプンなどが多く含まれるため一般的な浄水施設では対応しきれず、悪臭問題などにも発展していたらしいです。
香川県を中心として大阪などでも利用されているらしく、2004年頃から利用されているそうです。
すごすぎますね香川県、うどんの排水で環境問題にまで発展するほどうどん県ですね。
想像以上のうどん具合です、うどん愛が強すぎる。
私もうどんは大好きですが、香川県の本気を見た気がしました。
香川ではコシの強いうどんとすごく緩いうどんがあるそうですね、私はコシが強い方が好みです。
地域ネタって面白いです、思いもつかないような内容が多いですし。
北海道では寒さの関係で各家庭に灯油用のタンクが備え付けてあったりするそうですが、これも地域特有の特殊な装置ですね。
地元の人にとっては死活問題だったりするのでしょうけれど、そういった環境だからこそ思いつくアイデアというのがあるのだと感じますね。
エイプリルフールっていつからあるのか?

エイプリルフールはそもそも何が元になったものなのか、いつ頃から始まったことなのかもハッキリしていない。
あれだけ世界中でネタにしておいて、何が元なのかもハッキリしていないとは。
実際に調べた結果幾つかの候補はあるようですが、どれも信憑性に欠けるようですね。
元が何であったかはさておき、呼び方は違えど世界中に似たような風習があったことも事実だそうで、なんとも不思議な感じです。
とはいえ、今やエイプリルフールは独立した世界的なイベントとなっていますし、元が何であったかを考えるのは些末なことかもしれませんね。
企業でも個人でも、毎年気合の入ったネタを放り込んできますし、そのネタが人気を博したから商品化したなんて話もありますよね。
逆に真面目な告知なんかはエイプリルフールだと勘違いされてしまうそうで、しっかり避けるようにしているみたいです。
エイプリルフールだからこそ思いっきりふざけることができる一日があるというのもいいものですね、たまにやりすぎてる感じのもあるので程々にしてほしいとは思いますが。
麹菌って日本にしかないって本当?

日本では古くから麹菌を利用した発酵食品が発展してきているが、実は食品に適した麹菌は日本にしか存在していない。
麹菌はカビの一種であり、本来であれば毒を発生させてしまうものなのですが、日本で発酵に使われている麹菌は遺伝子の毒を発生させる部分が欠落しており、非常に良質な麹菌なのだそうです。
これは古くは種麹屋なんて職業があるくらいに良質な麹菌を厳選してきた過去があるからとのこと。
食に対するこだわりが強すぎるよ日本人は。
海外にもカビを使ったチーズとかありますけど、カビを少しずつ品種改良して安全にしてしまって、それを調味料や酒造りに活用してしまうというのが凄まじい。
日本酒も味噌も醤油も、麹菌があるからこそ製造できるものばかり、日本の食卓には欠かせない調味料です。
日本人ってこういうところがありますよね、どうにかして食べれるようにしてやろうって気概があるというか。
コンニャクイモとか、どうしてそこまで手間をかけてコンニャクを作ろうと思ったのか、最初に考えた人の執念が意味不明なレベル。
白い網のような見た目のキヌガサタケとかも、どうしてこんな見た目の物を食べようと思ったのかと不思議に思います。
まぁその執念や好奇心のおかげで今の日本食があると思うと、感謝しかないのですが。
傘ってずっと進化していない気がするけど気のせい?

傘の形状は4000年前の古代エジプトなどに存在を確認されているが、ほとんど変わっていない。
今のような開いたり閉じたりできるような傘になったのは13世紀のイタリア、しかし用途としては日傘であり、現代のような雨傘としての用途になったのは18世紀のイギリス。
4000年前から形状自体は変わってないということは、もうこれが最適解なのでしょうね。
閉じる向きが逆の傘だったり、折り畳めたり、楕円形のような傘も登場してはいますが、形状としてはほとんど同じですから。
ちなみにビニール傘の発祥は日本だそうで、1958年に浅草で生まれたそうですよ。
また、個人の傘の所有率は日本がほぼ100%で世界一、雨に濡れることを嫌がる率も日本人はかなり高いそうです。
海外だと雨が降ったならそもそも外出しないとか、傘を差すよりコートを頭から被るとかするそうですね。
もしも傘が進化するのだとしたら、それは日本発祥になりそうな感じですね。
感想

今回も気になってたことをたくさん発散できました、個人的には香川県の”高濃度うどん排水処理施設”が衝撃的でしたね。
こういう記事にするには内容が薄いけど気になっていたことって結構日々の中に転がっているので、これからもちょっとずつ溜めては放出したいと思います。
個人的にも気軽にちょこっと調べられるので、結構楽しいのです。
それでは今回はこのあたりで。
あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。
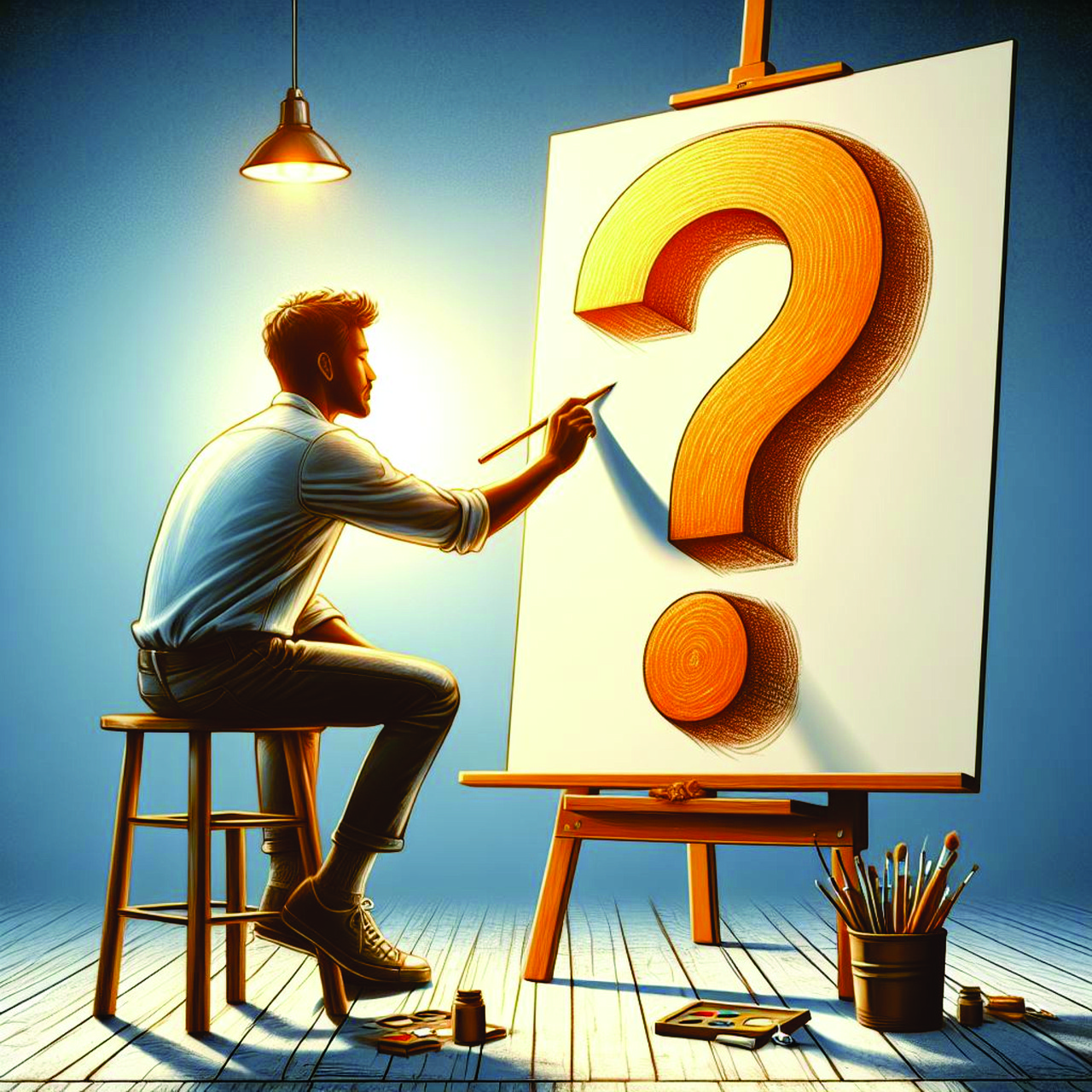


コメント